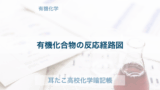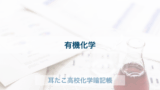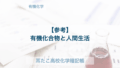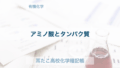- 耳たこ有機化学「高分子化合物と糖類」の暗記ページです。
- 四角い枠をクリックすると解答が表示され、下のボタンで一括表示・非表示の切替ができます。
- 耳たこ音読では音声ファイルを再生して要点を音読します。通学時間などのスキマ学習に最適です。
- 目次をクリックすると各セクションへ移動します。
高分子化合物
耳たこ音読|高分子化合物の基本
音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
高分子化合物は用語が多数結びついて生じる用語であり、重合体のくり返しの構成単位数を用語という。分子量は用語で表し、約1000以上で、決まった用語がない、加熱で軟化や性質する。分類と、分類に分けられる。
重合には、炭素間に結合をもつ分子が次々と反応する反応名、分子間で分子などがとれて多数結合する反応名などがある。
糖類
耳たこ音読|単糖の性質
音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
一般式式で表される化合物を分類名といい、別名とも呼ばれる。
分類名は、それ以上反応されない糖類の最小単位であり、酵素の作用で生成物と生成物に分解される。これを反応名という。
炭素数が5のものを分類名といい、化合物などがある。
炭素数が6のものを分類名といい、単糖は別名とも呼ばれ、水に溶けると異性体と異性体と構造の状態になる。
単糖は別名とも呼ばれ、水に溶けると構造や構造の構造と構造の状態になる。
単糖はグルコースと異性体の関係である。
単糖と単糖は分類名とよばれ、構造を形成でき、官能基をもつため○○性を示す。
また、単糖は分類名とよばれ、○○性を示す構造をもつ。
耳たこ音読|二糖の性質
音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
単糖2分子が反応名したものを分類名といい、この結合を結合という。一般式は式となる。
二糖は別名とも呼ばれ、異性体2分子が反応名した構造を持つ。また、物質を酵素の酵素で加水分解することでも得られる。構造があり、○○性を示す。酵素の酵素で加水分解されて、生成物となる。
二糖は別名とも呼ばれ、異性体と化合物が反応名した構造をしている。○○性はないが、酵素の酵素で加水分解されて、生成物と生成物になり、これを用語といい、○○性を示すようになる。
二糖は異性体2分子が反応名した構造を持つ。また、物質を酵素の酵素で加水分解することでも得られる。構造があり、○○性を示す。酵素の酵素で加水分解されて、生成物となる。
二糖は別名とも呼ばれ、化合物と化合物が反応名した構造をしている。構造があり、○○性を示す。酵素の酵素で加水分解されて、生成物と生成物となる。
糖類の分類
一般式は、Cn(H₂O)m
分類名
炭素数が5のものを分類名といい、単糖C₅H₁₀O₅などがある。
炭素数が6のものを分類名といい、
単糖C₆H₁₂O₆別名、
単糖C₆H₁₂O₆別名、
単糖などがある。
分類名
一般式は、C₁₂H₂₂O₁₁
分類名
一般式は、(C₆H₁₀O₅)n
単糖の性質
② 水に溶かすと、下の3つの構造が用語となる。
・化合物
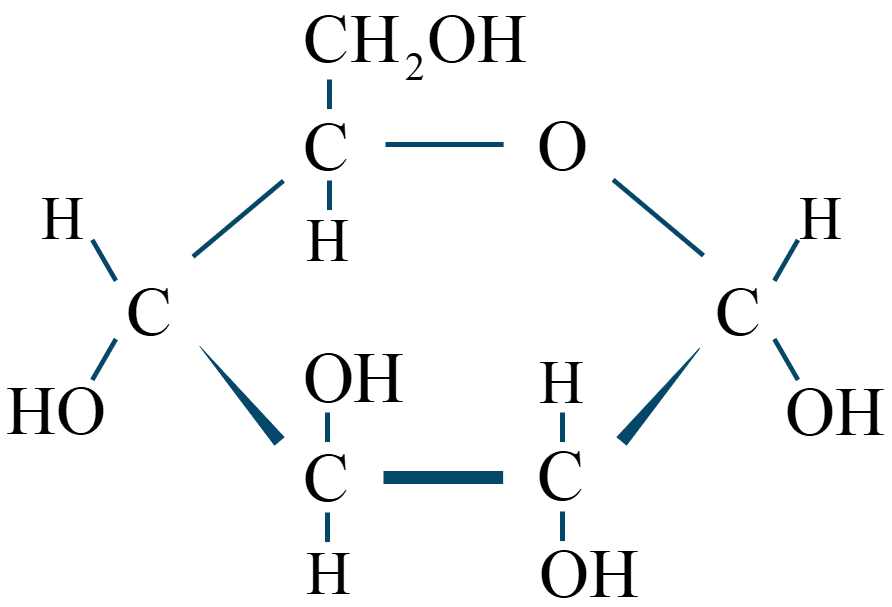
⇅
・化合物・形状構造
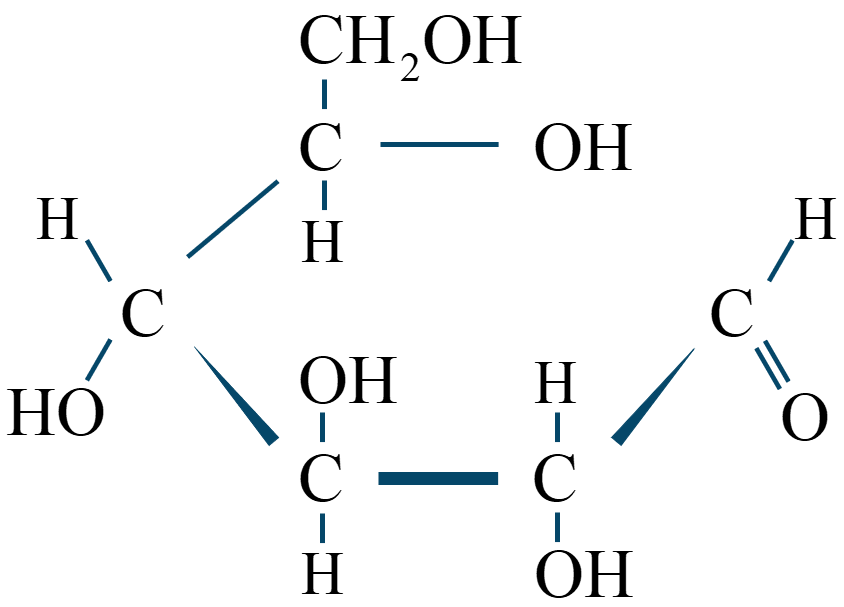
⇅
・化合物
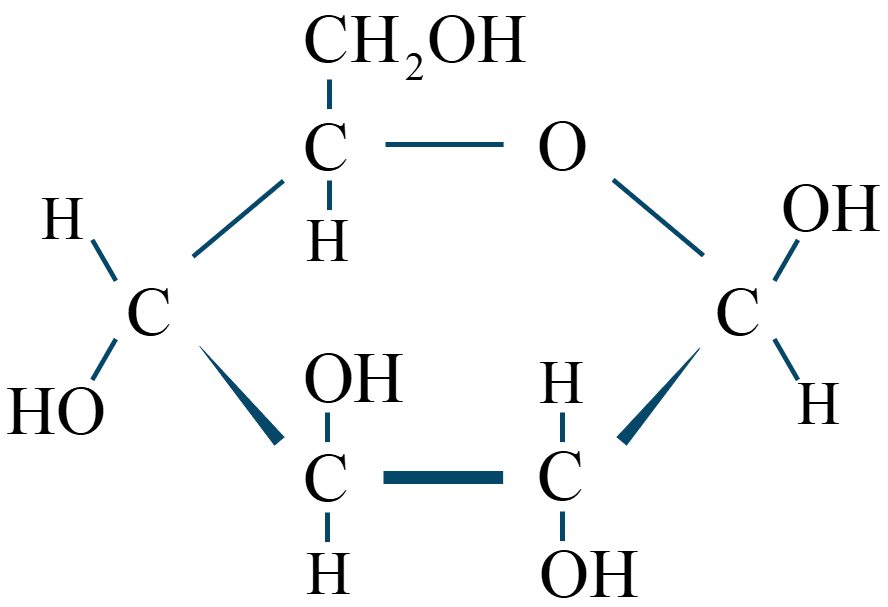
③ 化合物は構造を形成でき、官能基をもつので○○性を示す。よって、反応や物体の還元を示す。
④ 酵素により、化合物と化合物に分解される。これを用語という。
■ 単糖・別名
② 水に溶けやすさ、溶かすと下の3つの構造と化合物2種の合計5種類が用語になる。
・化合物・形状構造
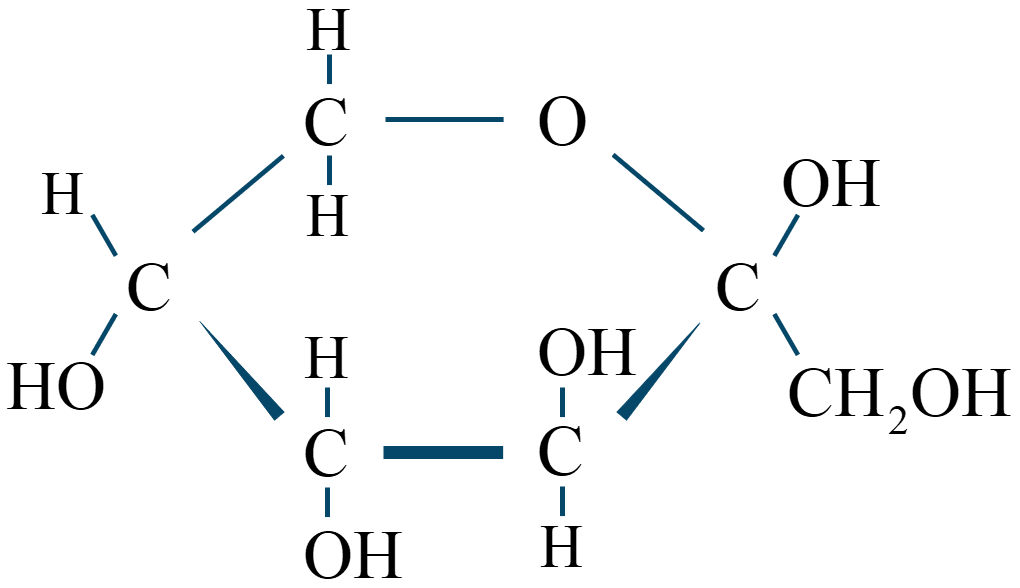
⇅
・化合物・形状構造
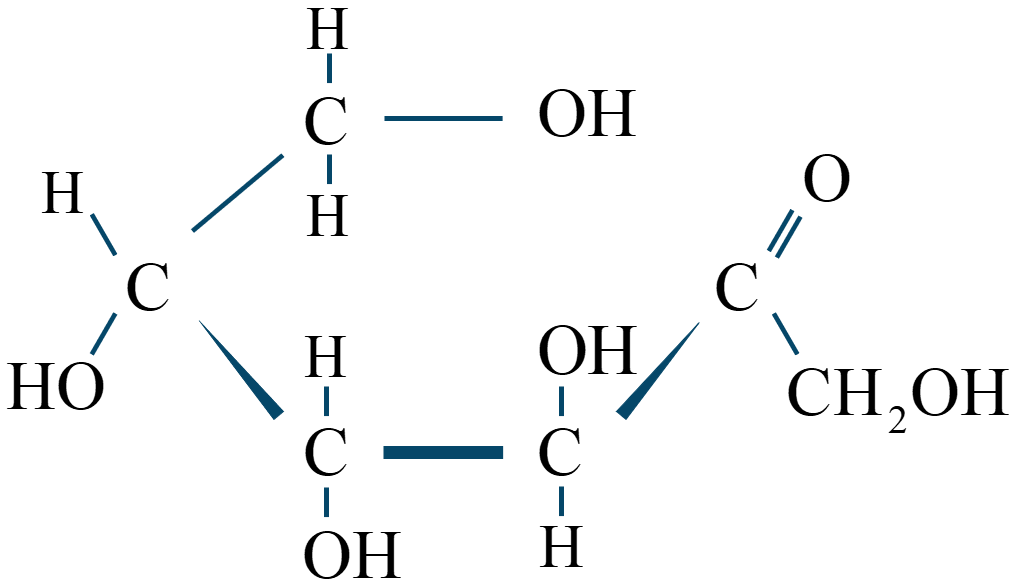
⇅
・化合物・形状構造
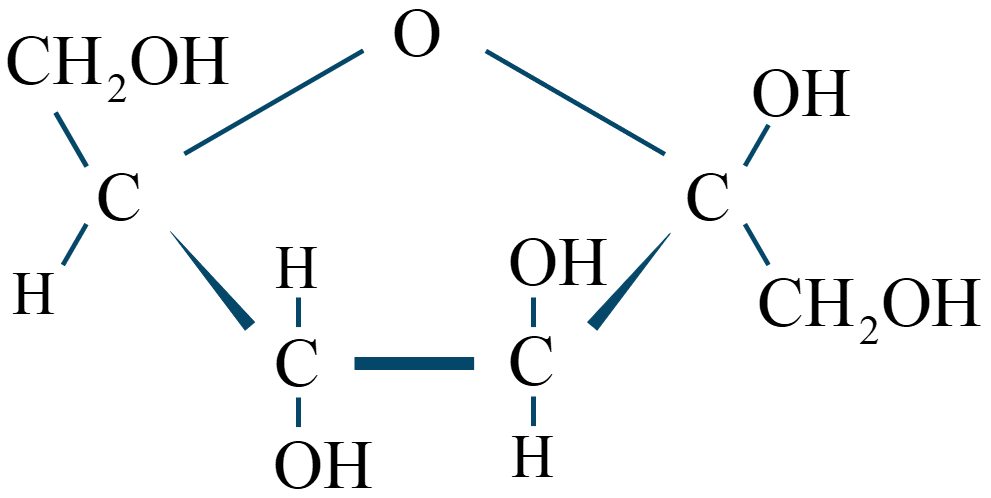
③ 化合物は官能基をもちアセトンなどとは違い○○性を示す。
■ 単糖
② ○○性を示す。
・α-ガラクトース
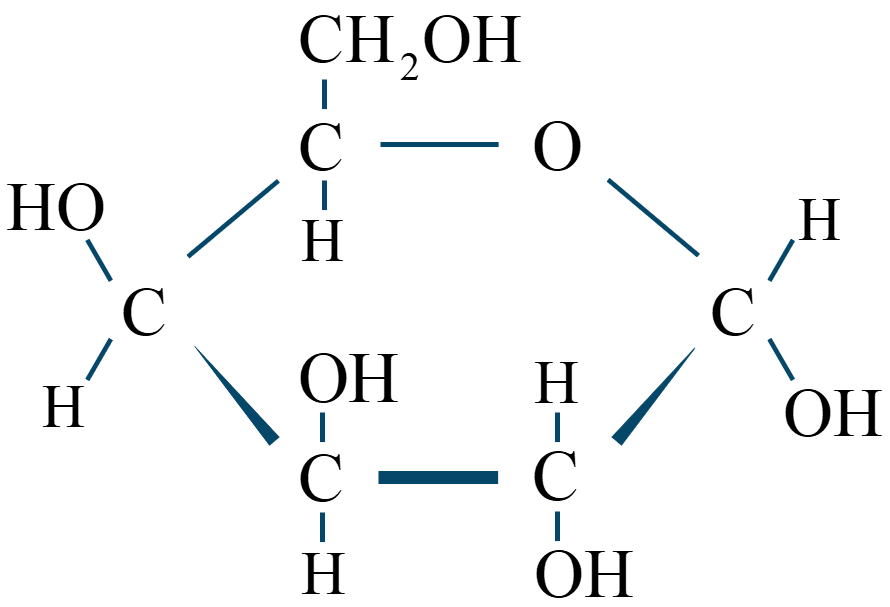
・β-ガラクトース
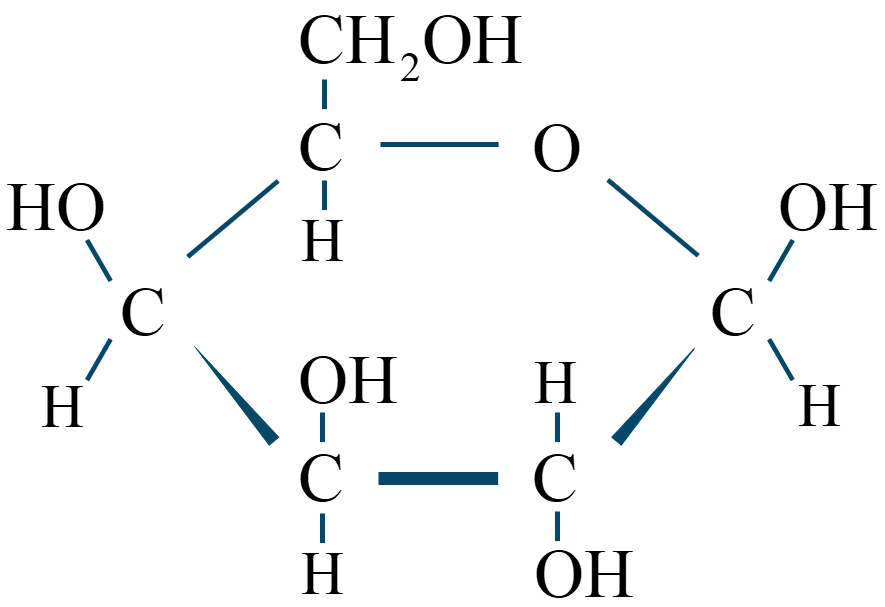
二糖の性質
■ 二糖・別名
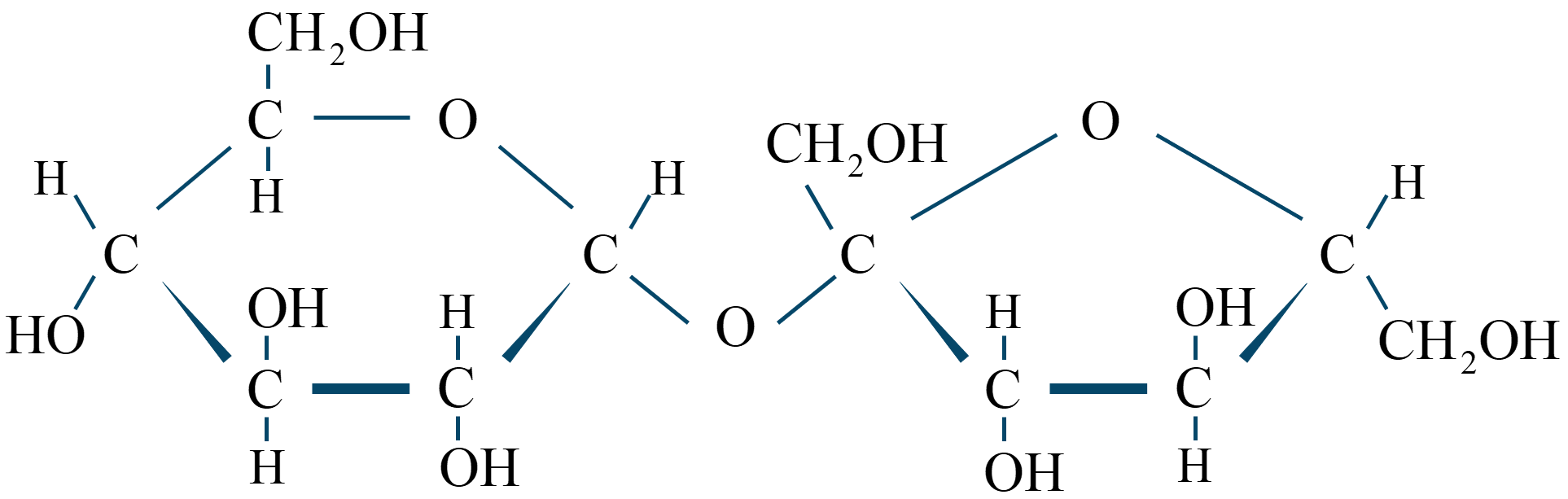
② ○○性を示さない。
③ 酵素で加水分解されて、単糖と単糖の混合物である用語となり○○性を示すようになる。
■ 二糖・別名
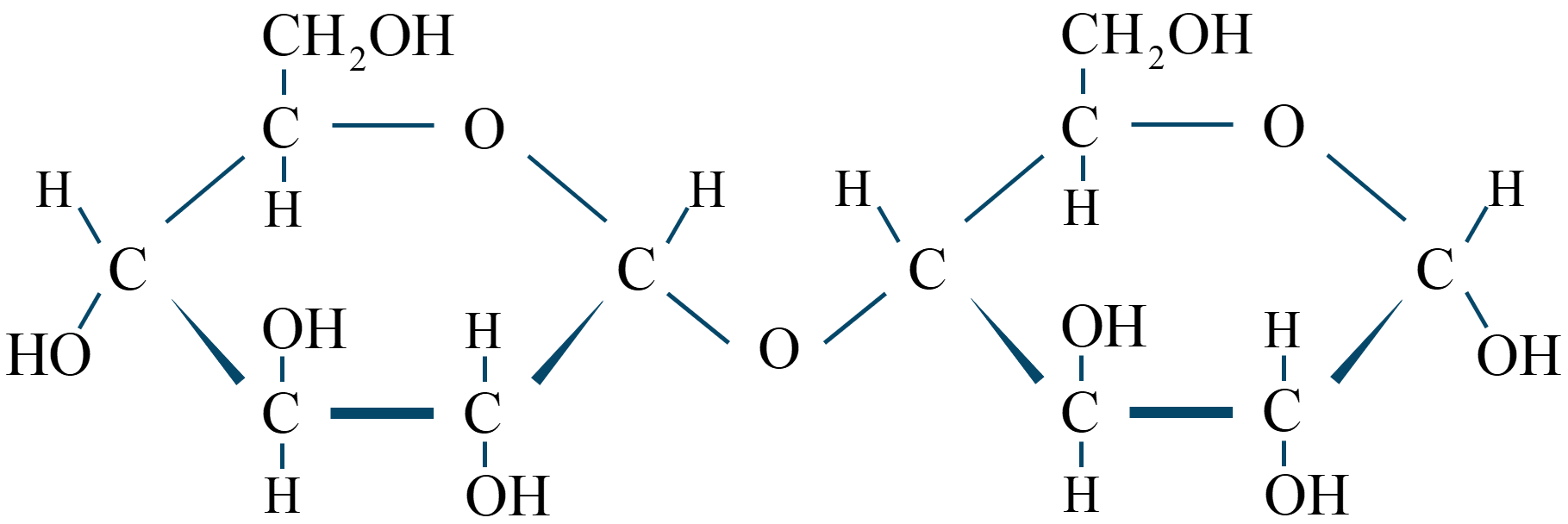
② 構造があり、水に溶けると開環し官能基となる。よって、○○性を示す。
③ 酵素で加水分解され、単糖2分子となる。
④ 多糖を酵素で加水分解することで得られる。
■ 二糖
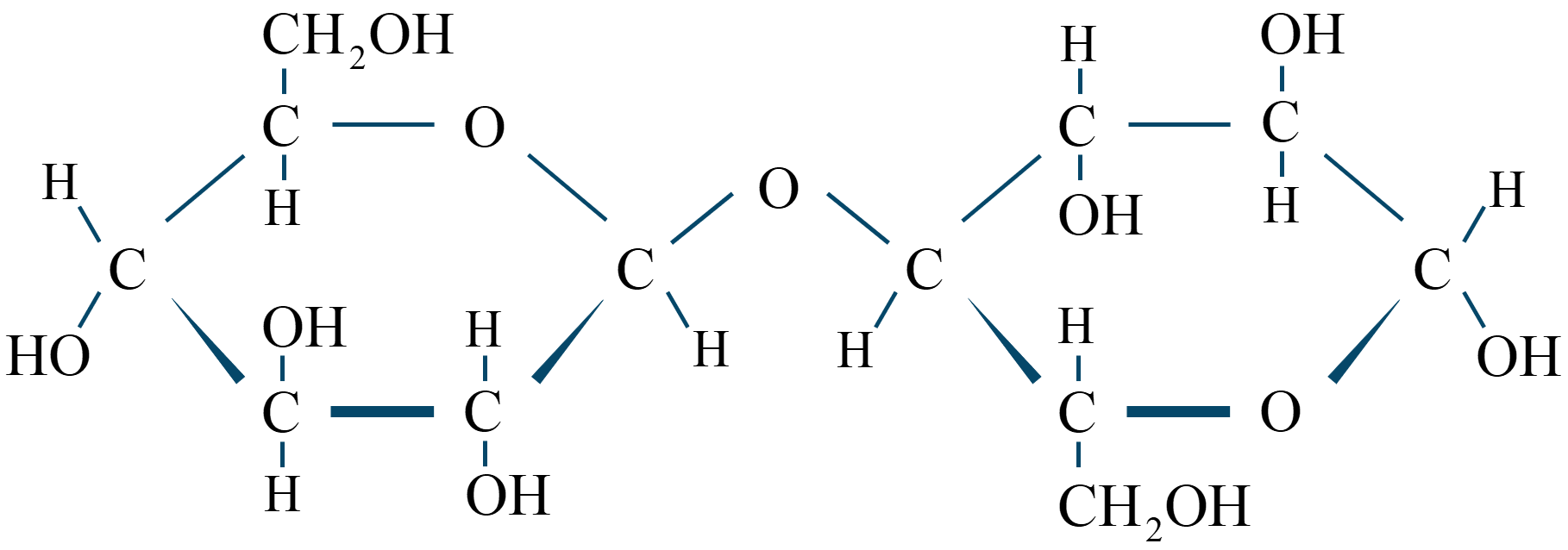
② ○○性を示す。
③ 酵素で加水分解され、単糖2分子となる。
④ 多糖を酵素で加水分解することで得られる。
■ 二糖・別名
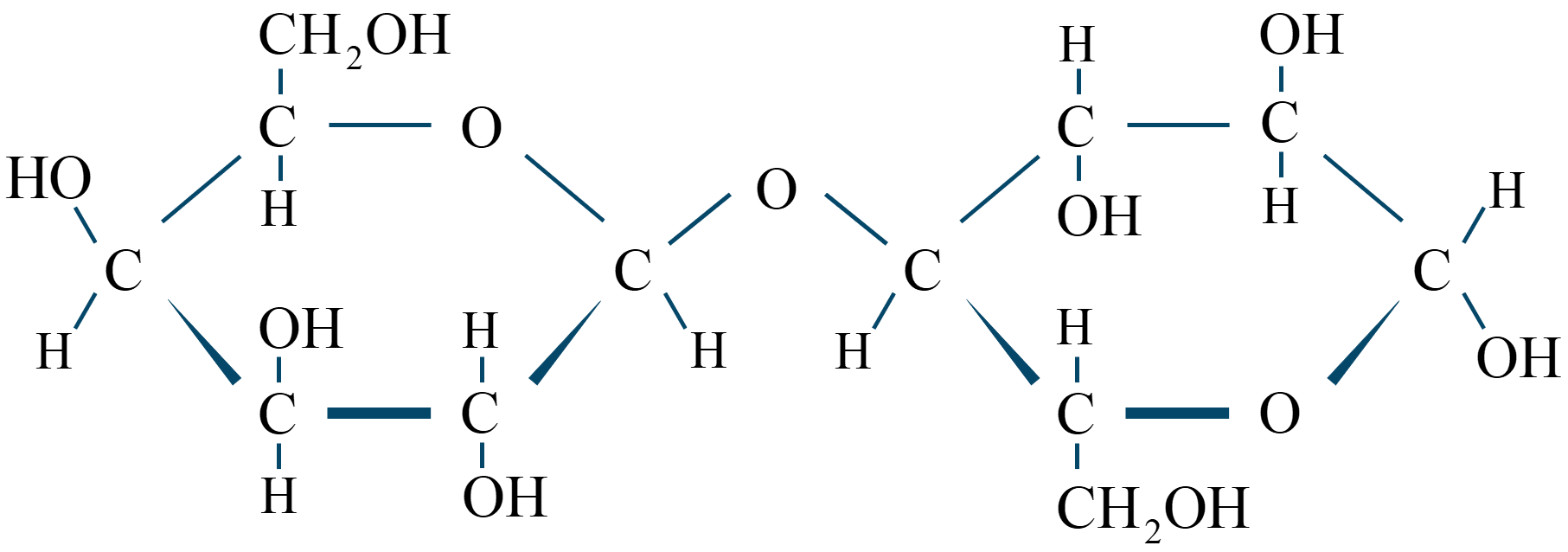
② 構造があり、水に溶けると開環し官能基となる。よって、○○性を示す。
③ 酵素を用いて単糖と単糖に加水分解される。
多糖
耳たこ音読|多糖の性質
音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
分類名は、多数の分類名が結合したものをいう。
多糖は、多数の構成が反応名した構造で、多数の結合を持つ。分子式は式である。デンプンには、水に溶ける構造で構造の分類名と、熱水に溶けにくい枝分かれした構造の分類名がある。どちらも反応で色に呈色する。また、酵素の酵素を加えると、加水分解されて生成物となり、さらに加水分解すると生成物となる。
多糖とは別名ともいい、アミロペクチンより構造が多い。反応で色に呈色する。
多糖は、多数の構成が反応名した構造で、結合を持つ。分子式は式であり、分子量が大きく、分子間の結合が強く、物質にも溶けにくい。また、○○状の結合した構造をしており、ヨウ素デンプン反応を示さない。酵素の酵素を加えると、加水分解されて生成物となる。物質に酸と酸の混合物(用語)を作用させると、分類名である生成物が得られる。
多糖の性質
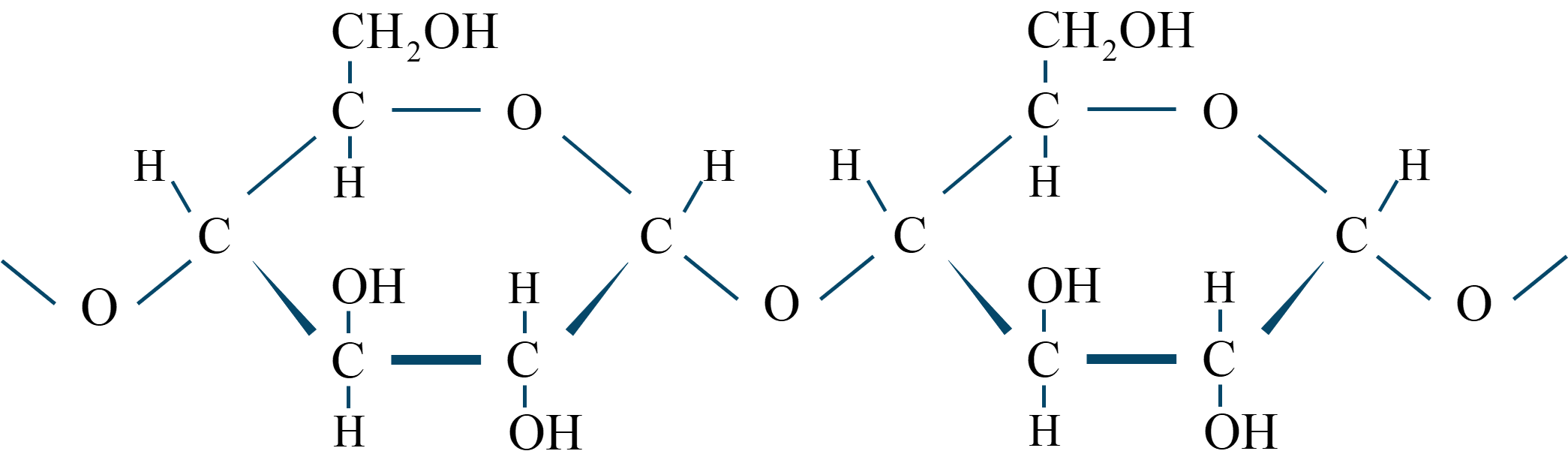
② 形状構造をしており、この中に単体が入ると用語する。これを反応という。
③ デンプンに酵素を加えると、二糖に加水分解される。また、物質名(酸)を加えると一気に単糖まで加水分解される。
■ デンプンの種類
分子量
水溶性に溶ける
ヨウ素デンプン反応
色
分子量
水に水溶性
ヨウ素デンプン反応
色
■多糖
② デンプンに構造が似ているが、形状がさらに多い。
③ ヨウ素デンプン反応で色を示す。
■多糖
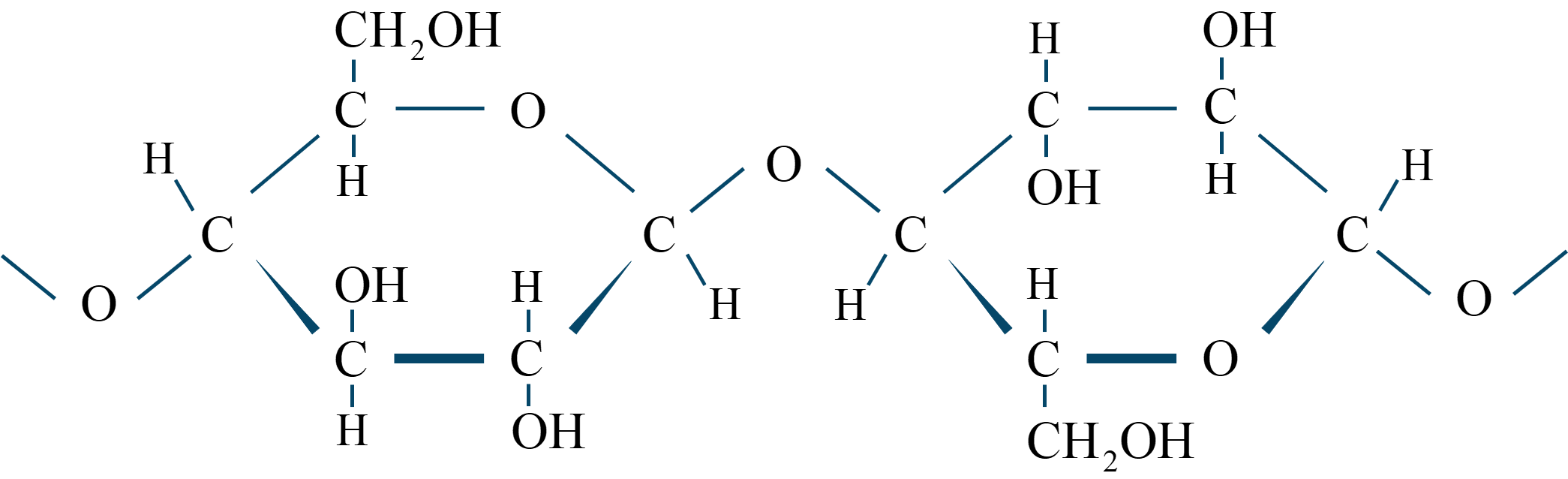
② 植物の用語の主成分。
③ 分子量が数以上で、熱水にも溶けやすさ。
④ β-グルコースが表裏表裏と結合して、形状構造をしており、反応を示さない。
⑤ セルロースに酵素を加えると、二糖に加水分解される。また、物質名(酸)を加えると一気に単糖まで加水分解される。
⑥ 濃硝酸と濃硫酸との混合物の混合物を加えると、分類名である化合物が得られる。
セルロース工業
耳たこ音読|セルロースと繊維
音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
セルロースを試薬で反応して生成物とする。これを反応すると生成物が得られ、これを繊維名といい、分類名である。
また分類は、セルロースを試薬で溶かして再生した繊維の繊維名と、セルロースを溶液と試薬を用いて中間体にしたあと、再生した繊維の繊維名がある。繊維名の形状のものが用語である。
再生繊維
別名ともいう。
■ 再生繊維
半合成繊維
・化合物
[C₆H₇O₂(OH)₃]n
↓アセチル化
・化合物
[C₆H₇O₂(OCOCH₃)₃]n
↓加水分解
・半合成繊維( アセテート繊維 )
[C₆H₇O₂(OH)(OCOCH₂)₃]n
反応経路図演習|糖類
この単元の反応経路図の演習問題です。
化合物名をクリックすると構造式が表示されます。
スクロースの反応経路図
α-グルコース
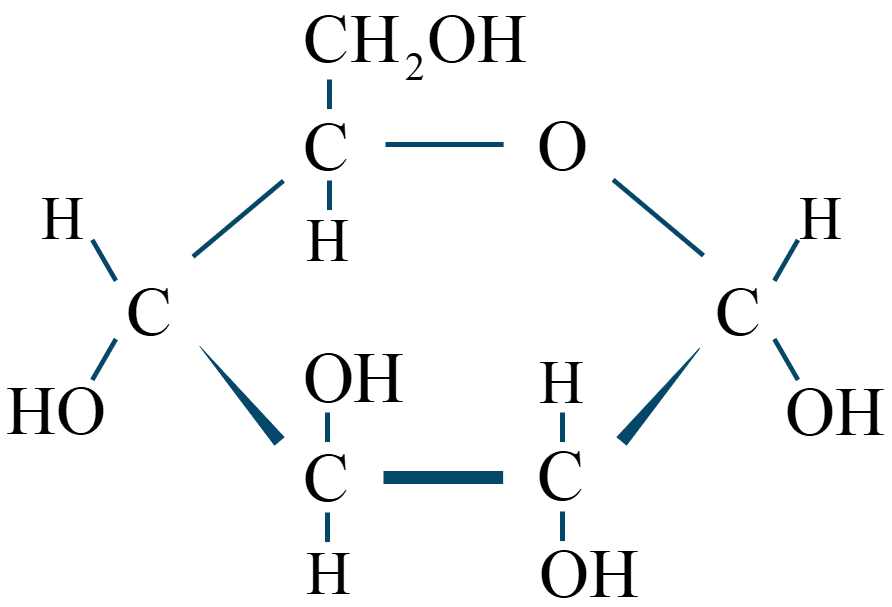
β-フルクトース
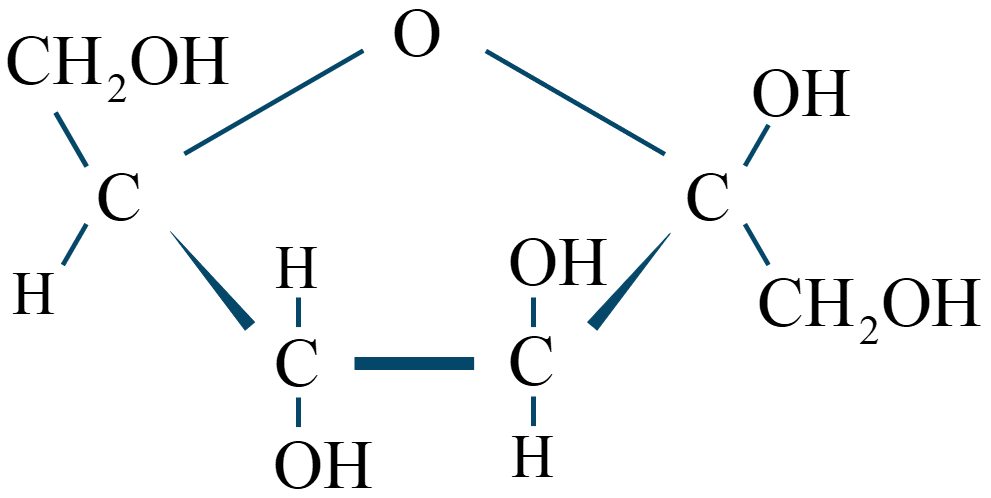
スクロース
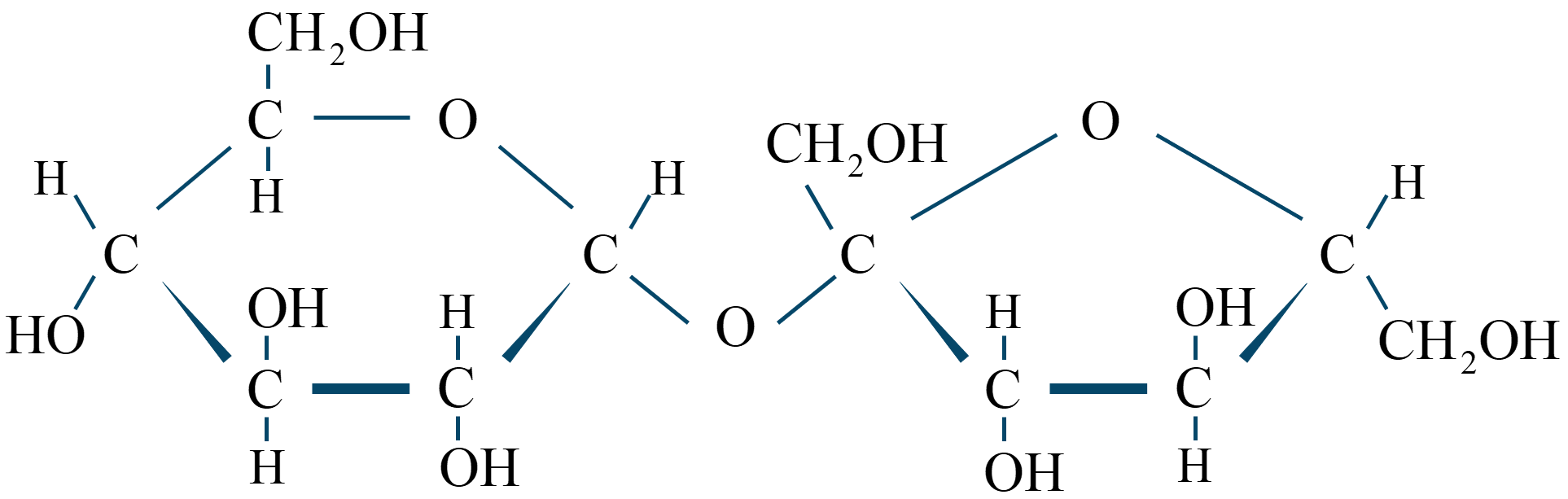
① 反応して結合ができる。
② 酵素で加水分解する。
マルトースの反応経路図
α-グルコース
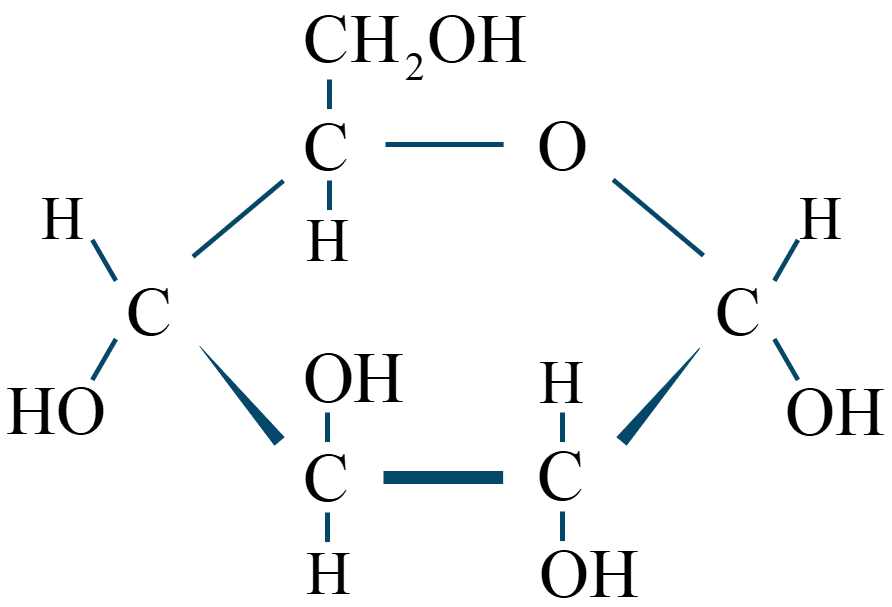
マルトース
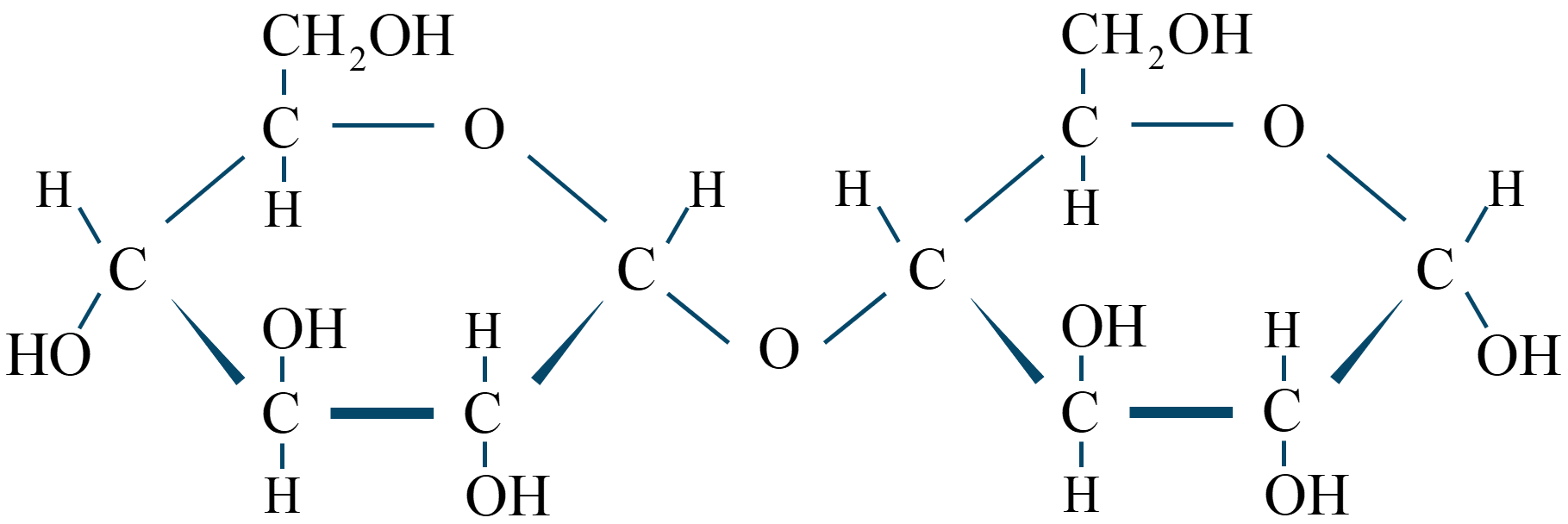
① 2分子を反応して結合ができる。
② 酵素で加水分解する。
③ 次々と反応して多数の結合ができる。
④ 酵素で加水分解する。
セロビオースの反応経路図
β-グルコース
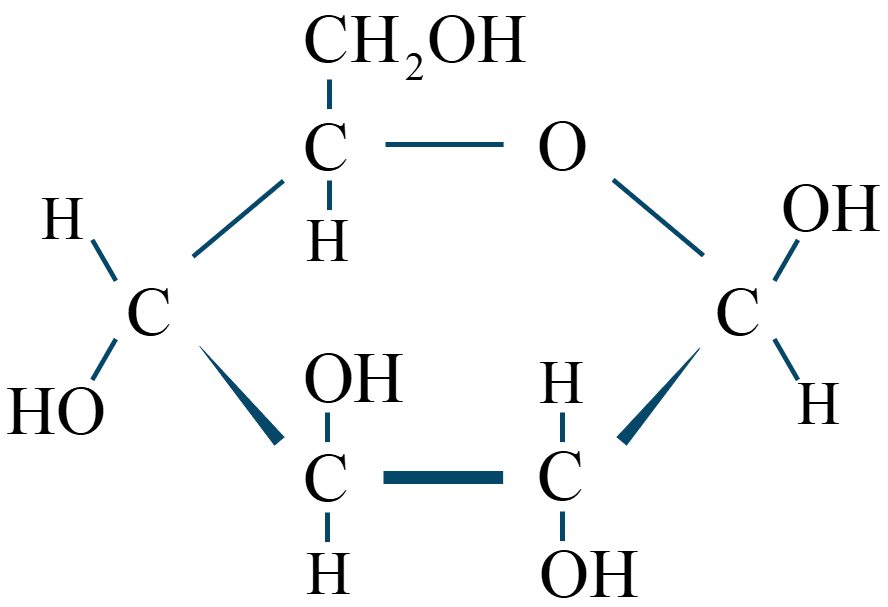
セロビオース
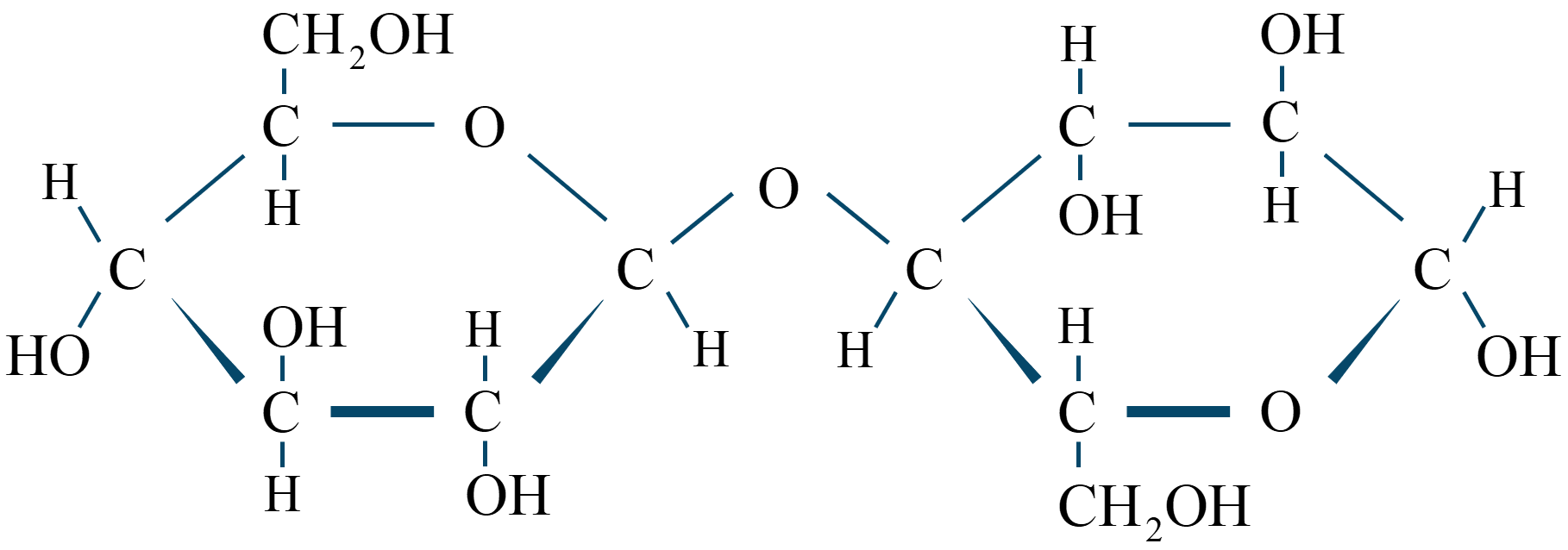
① 2分子を反応して結合ができる。
② 酵素で加水分解する。
③ 次々と反応して多数の結合ができる。
④ 酵素で加水分解する。