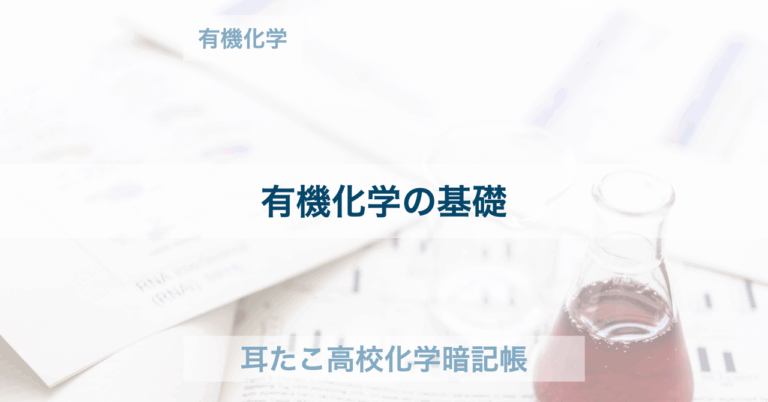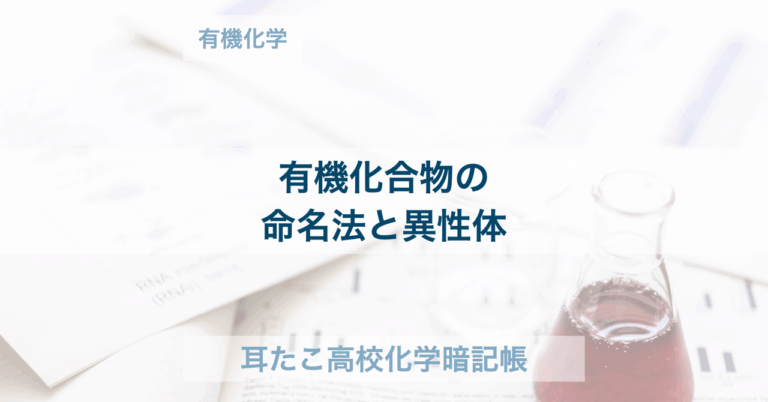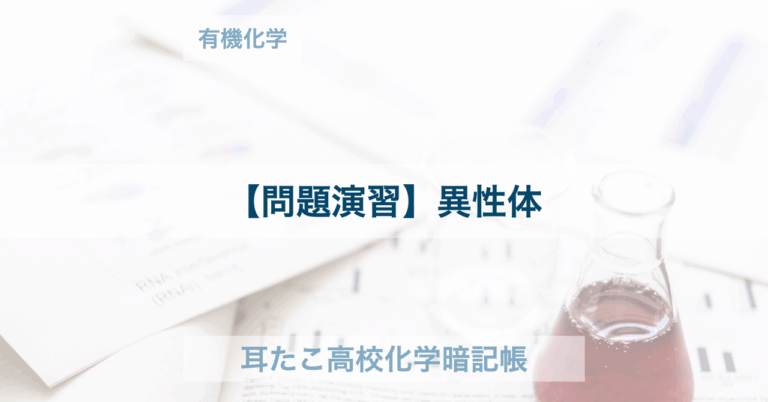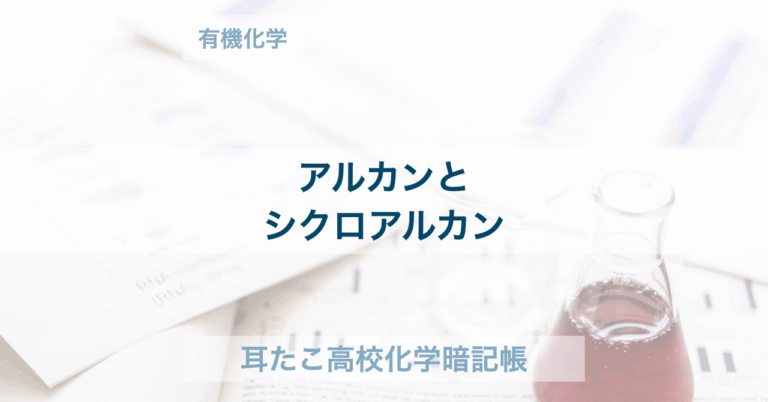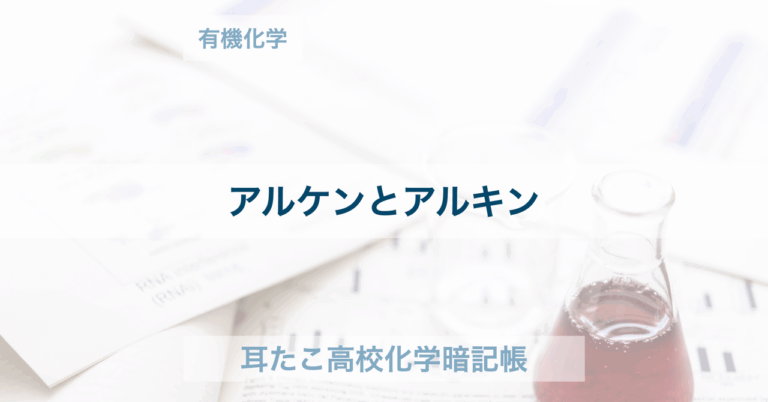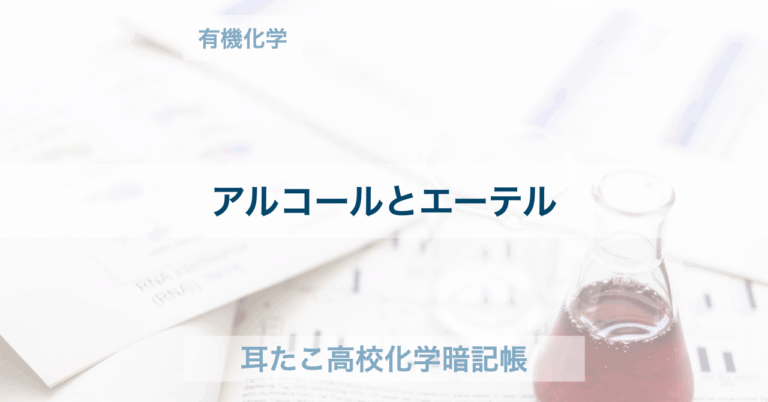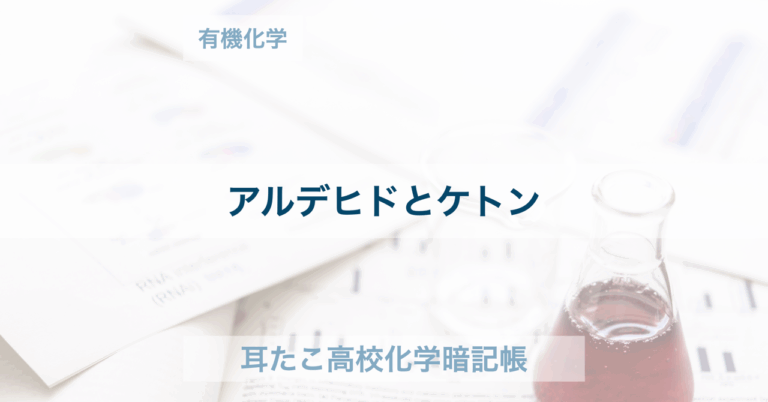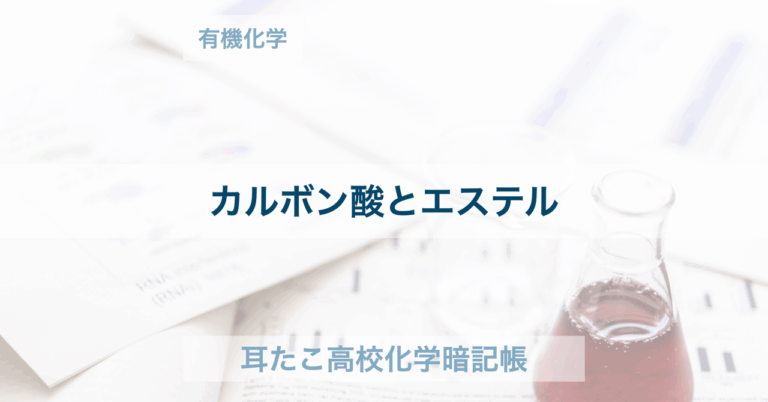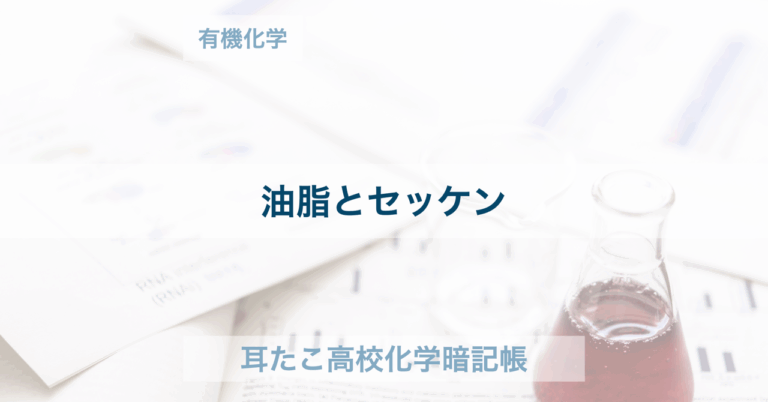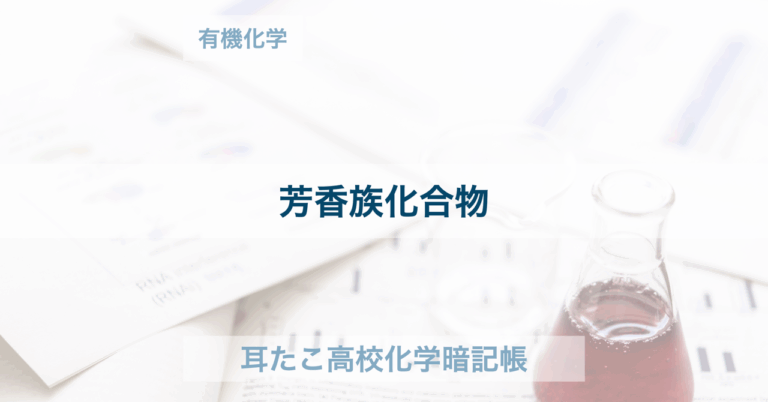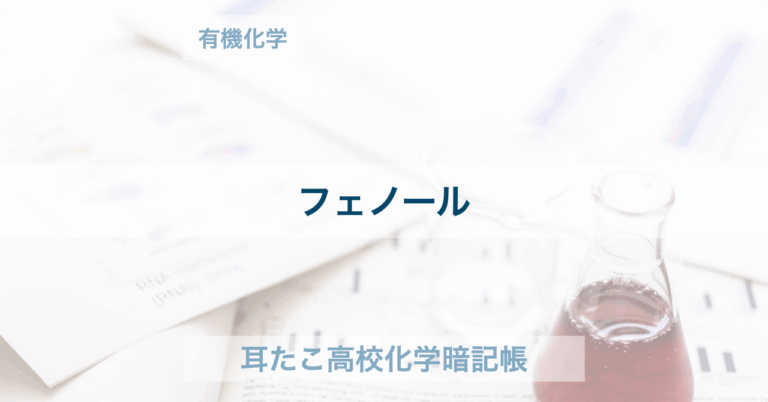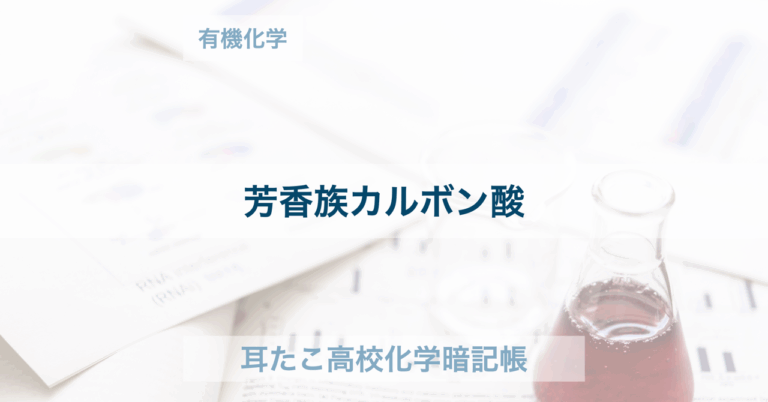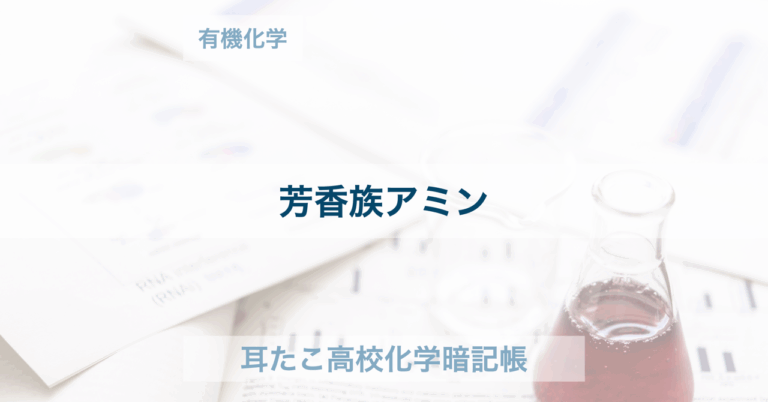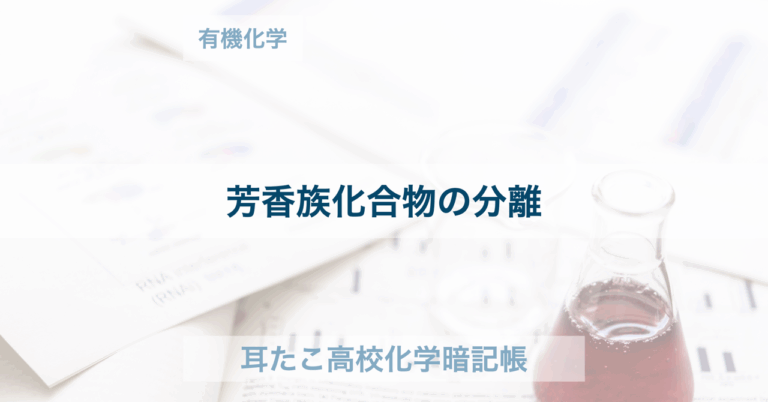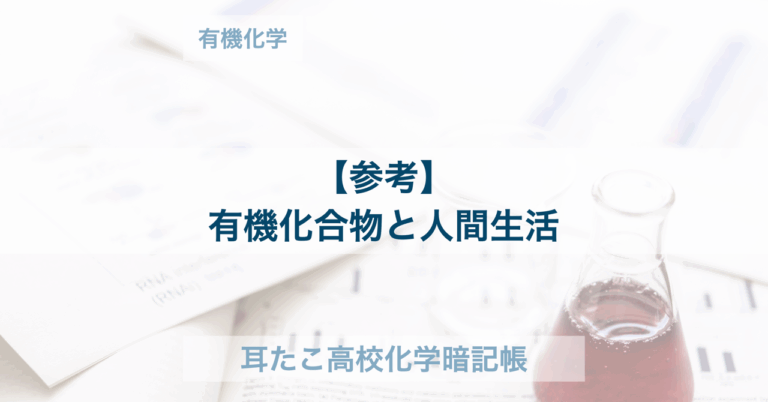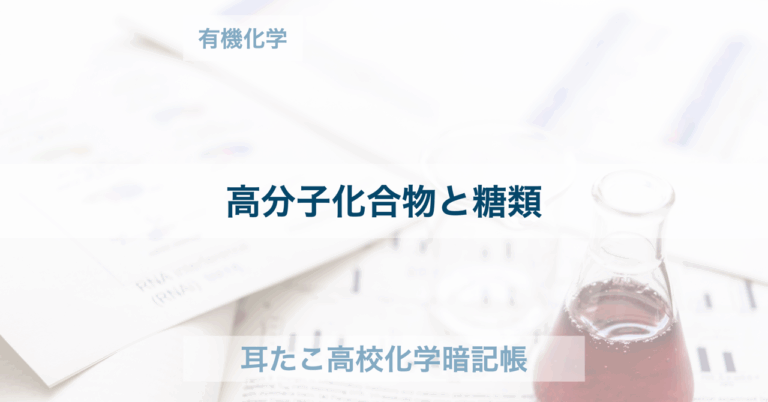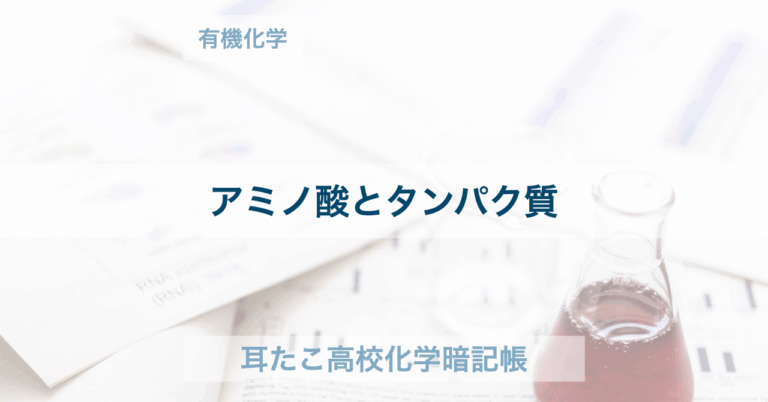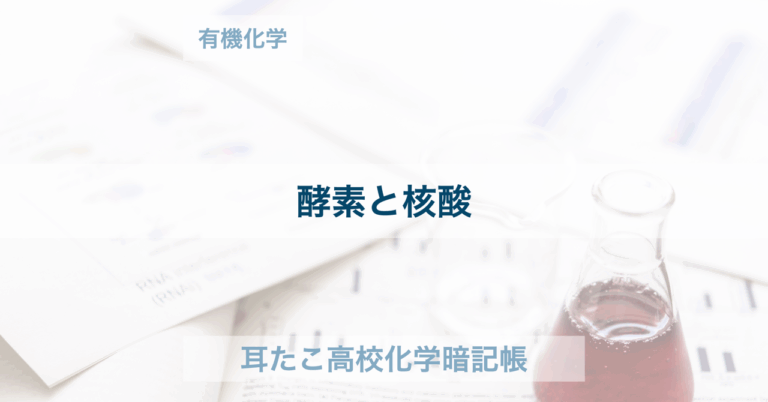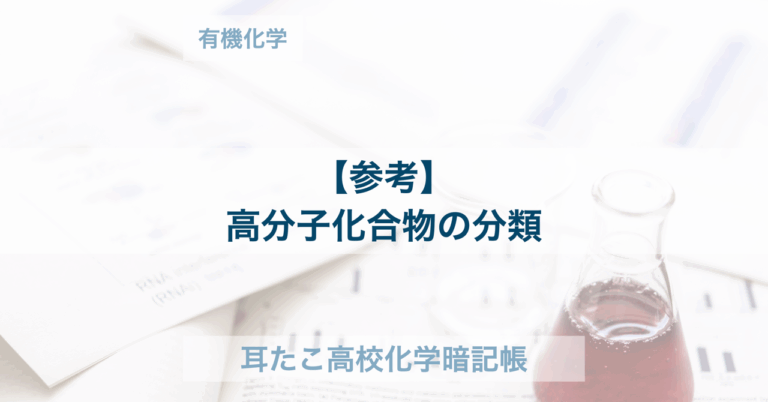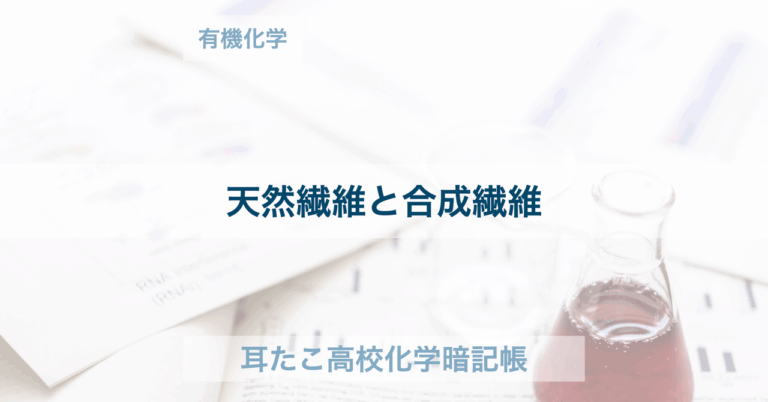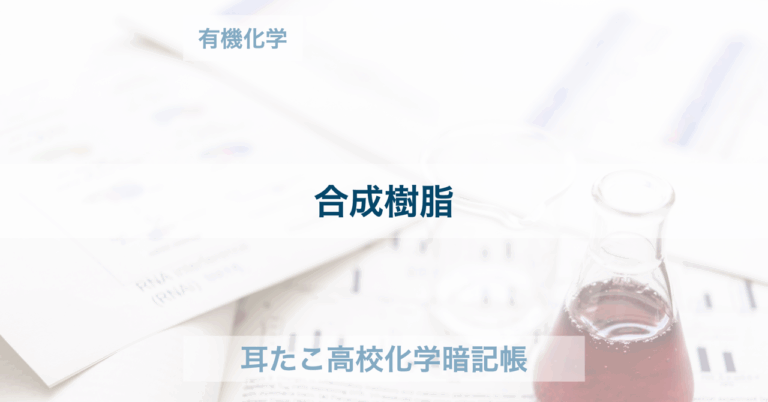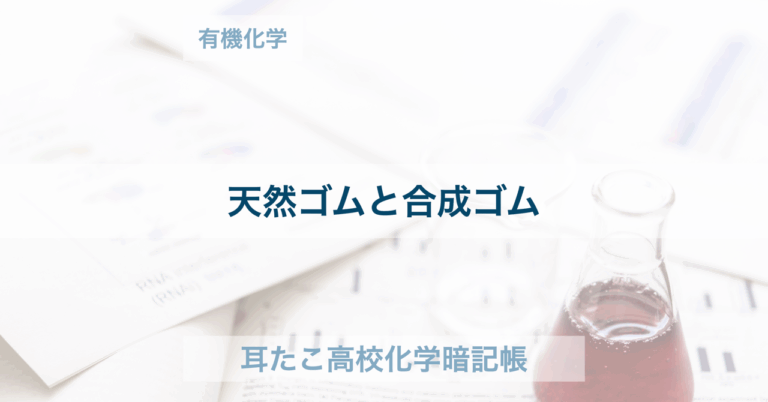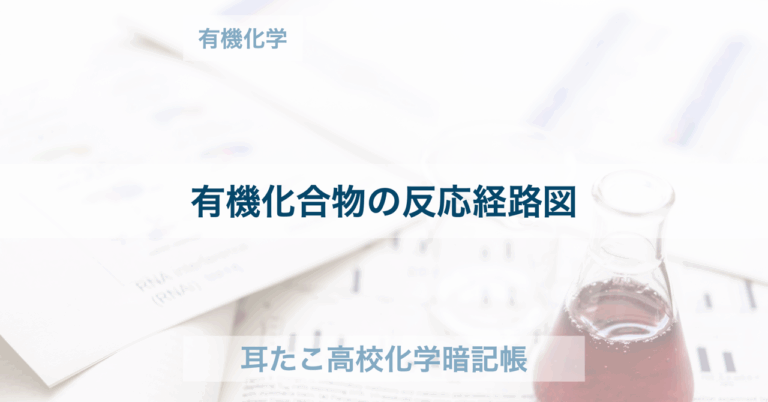スポンサーリンク
有機化学分野単元一覧

- 耳たこ高校化学暗記帳の「有機化学のまとめ」ページです。
- 四角い枠をクリックすると解答が表示され、下のボタンで一括表示・非表示の切替ができます。
- 耳たこ音読では音声ファイルを再生して要点を音読します。通学時間などのスキマ学習に最適です。
- 目次をクリックすると各セクションへ移動します。
目次
耳たこ音読まとめ|脂肪族炭化水素
■ 音声プレイヤー※音が出ます!
有機化学|脂肪族炭化水素の分野の音声ファイルをまとめたものです。「有機化学の基礎」から「油脂とセッケン」までの音声が流れます。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
有機化学|脂肪族炭化水素の分野の音声ファイルをまとめたものです。「有機化学の基礎」から「油脂とセッケン」までの音声が流れます。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
有機化学の基礎
有機化合物の基本と成分元素の分析
有機化合物は元素を基本として、元素、元素、窒素、硫黄などで構成され、その種類は分類名に比べて非常に多い。
有機化合物は構成からなり、融点や沸点は高低ものが多い。水には溶けやすさものが多く、物質に溶けやすい。燃焼しやすく、化合物と化合物などを生じる。
炭素・水素・酸素だけからなる有機化合物の分析方法は、化合物とともに完全燃焼し、化合物と化合物を生成する。化合物管を通して化合物を吸収し、質量の変化から元素の質量を量る。次に、物質管を通して化合物を吸収し、質量の変化から元素の質量を量る。元素の質量は全体の質量から量る。これより、質量÷原子量の比から○○式が決まり、分子量から○○式が決まる。
有機化合物の命名法と異性体
「問題演習】異性体
アルカンとシクロアルカン
アルカン
一般式式で表される炭化水素を分類名といい、用語炭化水素である。炭素数が少ない順に、化合物、化合物、化合物、化合物、化合物、化合物などがある。
分子量が大きくなると性質や性質が大きくなり、状態はメタンからブタンまでは状態であり、ペンタンやヘキサンは状態である。
炭素原子数が4つ以上の化合物、化合物、化合物は用語が存在する。
炭素原子間はすべて結合であり、これを軸に性質できる。
水には溶けやすさが、物質には溶けやすさ。反応性が乏しいが、条件を用いて元素群と反応を示す。
メタンの性質
化合物は、色・臭いの状態で、分子は構造をしている。実験室的製法は、化合物に化合物を加えて加熱する。
メタンは反応を示し、条件を当てることで化合物と反応し、水素Hが次々に置き換わる。これにより、生成物、生成物、生成物、生成物が生成される。物質名は別名別名、物質名は別名別名と呼ばれる。
シクロアルカン
分類名は一般式式で表され、分類名と用語の関係である。また、構造の構造をもつ用語炭化水素で、性質は分類名に似ている。
炭素数が3の化合物、炭素数が4の化合物、炭素数が5の化合物、炭素数が6の化合物などがある。
アルケンとアルキン
アルケン
一般式式で表される炭化水素を分類名といい、化合物、化合物、化合物などがあり、これらはすべて状態である。
アルケンは結合を1つもつ用語炭化水素であり、炭素原子間の二重結合は用語できない。二重結合の片方が切れて他の原子と結合する反応を示す。また、化合物などは異性体種(用語)がある。
エチレンの性質
化合物は無色の状態で、すべての原子が構造にある。実験室的製法は、化合物に酸を加えて温度で加熱すると、反応が起こり得られる。
エチレンは、結合の片方が切れる反応を示す。臭素Br₂との付加反応では、生成物が得られ、臭素水の色が色になる。水素H₂との付加反応では、触媒を触媒として生成物が得られる。水H₂Oとの付加反応では、触媒下で生成物が得られる。
多数の物質名分子が次々に反応すると、高分子となる。この反応を反応名という。
アルキン
一般式式で表される炭化水素を分類名といい、化合物、化合物、化合物などがあり、すべて状態である。
アルキンは結合をひとつもつ分類名炭化水素であり、炭素原子間の三重結合は性質できない。三重結合のひとつが切れて他の原子と結合する反応を示す。また、結合間距離は長い順に、結合>結合>結合となる。
アセチレンの性質
化合物は色・臭いの状態で、すべての原子が構造にある。実験室的製法は、化合物(別名別名)に化合物を作用させることで得られる。工業的製法は、化合物を熱分解することで得られる。
アセチレンは、結合のひとつが切れて他の原子と結合する反応を示す。水素H₂との付加反応では、触媒を触媒として生成物が得られ、さらに付加反応すると生成物が得られる。臭素Br₂との付加反応では、生成物が得られる。水H₂Oとの付加反応では、触媒下で反応して生成物となるが、不安定であり生成物となる。塩化水素HClとの付加反応では、生成物が得られ、酢酸CH₃COOHとの付加反応では、生成物が得られる。また、アセチレン3分子が反応すると、生成物となる。
アルコールとエーテル
アルコール
分類名は、炭化水素の水素原子を官能基で置き換えた構造をしている。アルコールは電離しないので、液性は液性である。ヒドロキシ基は○○性であり、結合を形成するため、アルコールの性質や性質は高い。分子量の小さいアルコール(分類名)は常温で状態であり、水に溶けやすさ。分子量の大きいアルコール(分類名)は常温で色と状態であり、水に溶けやすさ。
アルコールは、結合しているヒドロキシ基の数(用語)で分類される。化合物や化合物を分類名、化合物を分類名、化合物を分類名という。
また、ヒドロキシ基が結合している炭素原子に、他の原子が何個ついているかで分類し、これを用語という。他の炭素原子が数のときは分類といい、数のときは分類、数のときは分類という。
メタノールとエタノールの性質
化合物と化合物は色の状態であり、物質名は毒性である。ともに、単体の金属と反応して生成物を発生する。
メタノールの製法は、触媒下高温高圧で原料と原料を反応させる。エタノールの製法は、触媒下で原料に原料を反応させる。
エタノールは、反応を示し、酸を加えて温度で加熱すると、反応が起こり、生成物となる。また、酸を加えて温度で加熱すると、反応が起こり、生成物となる。
アルコールの酸化
分類を酸化すると生成物が得られ、さらに酸化すると生成物が得られる。
例えば、化合物を酸化すると生成物が得られ、さらに酸化すると生成物が得られる。また、化合物を酸化すると生成物が得られ、さらに酸化すると生成物が得られる。また、化合物を酸化すると生成物が得られ、さらに酸化すると生成物が得られる。
分類を酸化すると生成物が得られ、これ以上は酸化されない。例えば、化合物を酸化すると生成物となる。
分類は酸化されにくい。
エーテル
分類名2分子から化合物1分子が反応して得られるものを分類名という。化合物、化合物、化合物などがある。
エーテルは、2個の炭化水素基が結合で結びついている。同じ炭素数のアルコールと用語の関係にあるが、金属とは反応しない。また、水には溶けやすさ、物質として用いる。
化合物の反応で得られる化合物は、○○性の液体で○○性や○○作用がある。
アルデヒドとケトン
アルデヒドとケトン
分類名を酸化すると官能基をもつ分類名となり、分類名を酸化すると官能基をもつ分類名となる。炭素数が同じであれば、アルデヒドとケトンは用語の関係である。また、アルデヒドは○○性があり、酸化して分類名となるが、ケトンは還元性がないので用語されない。
化合物が酸化して得られる化合物は、色の状態で臭いがあり、毒性である。水に溶けやすさ水溶液となり、用途として用いる。
化合物が酸化して得られる化合物は、色で臭いがあり、○○性状態である。水や分類名に溶けやすさ。
化合物が酸化して得られる化合物はケトンであり、色で独特の臭いがある○○性の状態、○○性のがある。水に任意の割合で混ざる。また、アセトンは化合物の操作でも得られる。
アルデヒドの反応
分類名である化合物と化合物は○○性があるので、水溶液を加えて加熱すると、金属が析出する反応を示す。また、試薬を加えて加熱すると、色の化合物の沈殿が生じる反応が起こる。
試薬と試薬を加えると、色と状態である化合物が沈殿する。これを反応名といい、化合物、化合物、化合物、化合物が反応を示す。
カルボン酸とエステル
カルボン酸
分類を酸化して得られる分類は官能基をもつ。
分類は水に溶けやすさ、電離して液性を示す。カルボン酸は物質より強い酸で、炭酸水素塩を用語して化合物を発生しカルボン酸塩となる。また、金属と反応して生成物を発生する。
分類はカルボキシ基を1つもち、化合物や化合物などがある。
分類はカルボキシ基を2つもち、化合物や化合物などがある。
分類はカルボキシ基を2つもち結合をもつ。化合物や化合物などがある。
分類はカルボキシ基(-COOH)と官能基の両方をもち、化合物などがある。
カルボン酸の種類
化合物を酸化して得られる化合物は、色の臭いのある状態で毒性である。分子内に官能基をもつので○○性があり、反応を示す。また、酸を加えると反応が起こり、生成物を発生する。
化合物を酸化して得られる化合物は、色の臭いのある状態。用語の主成分であり、高純度の酢酸は融点が低く、別名と呼ばれる。また、酢酸2分子が反応すると、生成物が得られる。
分類は異性体種があり、配置の化合物、配置の化合物がある。化合物を加熱すると反応が起こり、生成物となる。
分類の化合物は、官能基と官能基の両方をもつ。中央の炭素原子にそれぞれ4つの異なる原子団がついており、この炭素原子を用語といい、異性体をもつ。
エステル
分類と分類に酸を加えて加熱すると反応が起こり、カルボン酸(-COOH)の基とアルコール(-OH)の基から化合物が取れて結合する。これを反応名という。
例えば、化合物と化合物をエステル化すると化合物となる。また、化合物と化合物をエステル化すると化合物となり、化合物と化合物をエステル化すると化合物となる。
分子内に結合をもつ化合物を分類名といい、常温で状態で香りをもつ。また、水に溶けやすさ。同じ炭素数の分類名と異性体の関係である。
エステルに酸を加えると反応し、生成物と生成物となる。また、エステルに塩基の水溶液を加えて反応すると、生成物と生成物となる。これを反応名という。
油脂とセッケン
油脂の性質
分子量の大きい分類名を分類名といい、二重結合のない分類名と二重結合のある分類名がある。
高級脂肪酸3分子と分類名の化合物を反応名することで、分類名が得られる。油脂は水には溶けないが、物質には溶けやすさ。
飽和脂肪酸からなる油脂を用語といい、常温で状態である。不飽和脂肪酸からなる油脂を用語といい、常温で状態である。
脂肪油の中で、空気中で酸化されて固まるものを用語という。また、脂肪油に金属を触媒として物質を付加して状態にしたものを用語という。
セッケンの性質
油脂を水溶液で反応名すると、物質が得られる。セッケンは○○性のイオン部分と○○性の炭化水素基部分からなる。
セッケンを水に溶かすと、○○性の部分を外側に向けて形状の用語を形成し、これを用語という。
セッケンは○○剤として働き、水の性質を低下させる。また、汚れを取り込み水中に作用する作用名がある。水に少し溶けて液性を示すが、物質には沈殿を生じるため、使用できない。
分類名と酸とのエステルである用語を溶液でけん化したナトリウム塩を物質という。合成洗剤は水溶液が液性であり、物質に対しても使用できる。
耳たこ音読まとめ|芳香族炭化水素
■ 音声プレイヤー※音が出ます!
有機化学|芳香族炭化水素の分野の音声ファイルをまとめたものです。「芳香族化合物」から「芳香族化合物の分離」までの音声が流れます。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
有機化学|芳香族炭化水素の分野の音声ファイルをまとめたものです。「芳香族化合物」から「芳香族化合物の分離」までの音声が流れます。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
芳香族化合物
芳香族炭化水素の性質
用語をもつ炭化水素を分類名といい、化合物、化合物、化合物、化合物などがある。
ベンゼン環は原子が構造の構造をしており、すべての炭素原子が構造にある。また、炭素原子間の距離はすべて等しく、その距離は結合より短く、結合より長い。
ベンゼンの用語は、配置、配置、配置の3種類の異性体が存在する。
ベンゼン環の側鎖の基は、反応されると官能基となる。
ベンゼンの性質
化合物は色の状態で臭いをもち、水には溶けやすさが、物質には溶ける。燃焼すると多量の物体を出す。また、すべての原子が構造にある。製法は、原料3分子を触媒下で反応させる。
ベンゼンに金属を触媒として高温高圧下で物質を付加させると生成物となる。また、条件を当てながら物質を付加させると生成物となる。
ベンゼンに金属を触媒として物質を作用させると反応が起こり、生成物となる。
酸と酸の混合物である物質を作用させると反応が起こり、生成物となる。また、酸を作用させると反応が起こり、生成物となる。
トルエンに高温で用語を作用させると反応が起こり、生成物が得られる。また、ベンゼンの用語である化合物には、異性体, 異性体, 異性体の用語がある。
フェノール
フェノール類の性質
ベンゼン環の炭素原子に直接官能基が付いた化合物を分類名といい、化合物や化合物などがある。化合物は、側鎖の炭素原子に官能基が付いているため、分類名である。
フェノール類は金属と反応すると生成物を発生する。また、試薬を加えると色に呈色する。
試薬と反応すると反応する。フェノール類は水に溶けやすさ液性を示し、酸性は物質より弱い。また、分類名と反応して生成物をつくる。
フェノールの性質
化合物は、水に溶けやすさ液性を示し、酸性は物質より弱い。溶液と中和反応して塩の塩をつくる。また、金属と反応すると生成物を発生して、塩となる。
フェノールの検出方法は、試薬を加えると色に呈色する。
フェノールに酸と酸の混合物である用語を加えて反応すると、色と状態である生成物となる。また、色の臭素水Br₂を加えて反応をすると、色の生成物が沈殿する。
フェノールに試薬を作用させると、反応して生成物となる。
フェノールの合成
フェノールの合成の方法は、化合物を反応して生成物を得る。これを溶液で中和反応させると、生成物となり、化合物の固体を混ぜて操作すると、生成物が得られる。これに酸を加えて弱酸の反応を行うと、フェノールC₆H₅OHが得られる。
ハロゲン化経由の合成では、化合物を反応して生成物を得る。これを溶液と高温高圧下で反応させて生成物となり、酸を加えて弱酸の反応を行うと、フェノールC₆H₅OHが得られる。
工業的製法の製法名では、化合物に化合物を触媒下で反応させて中間体とする。中間体を酸化すると中間体となり、これに酸を加えて分解すると、フェノールC₆H₅OHと生成物が得られる。
芳香族カルボン酸
芳香族カルボン酸の性質
ベンゼン環に直接官能基が結合した化合物を分類名という。
芳香族カルボン酸は水に溶けやすさが、液性を示し、強塩基と反応して生成物をつくる。溶液に入れると、弱酸の用語が起こり、生成物を発生し、溶ける。また、分類名と反応して反応名する。
芳香族カルボン酸の種類
化合物は色と状態で、水に溶けやすさが液性を示す。製法は、化合物を酸化剤で酸化して得られる。または、化合物を酸化して中間体とし、さらに酸化して物質名が得られる。また、安息香酸にアルコールと酸を加えて加熱すると、反応名して生成物となる。
化合物を酸化すると生成物が、化合物を酸化すると生成物が、化合物を酸化すると生成物が得られる。これらは価数の芳香族カルボン酸である。また、化合物は加熱すると反応が起こり、生成物となる。
サリチル酸の性質
化合物は、オルト位に官能基と官能基をもつため、分類名と分類名の両方の性質をもつ。色の状態で、水に溶けやすさ液性を示す。
製法は、化合物に高温高圧下で化合物を反応させて化合物をつくり、これに強酸を加えて弱酸の反応より化合物が得られる。
フェノール類としての反応は、試薬で色に呈色する。また、触媒を触媒として試薬と反応して生成物となり、官能基をもち、用途として用いる。
カルボン酸としての反応では、酸を触媒としてアルコールと加熱すると、反応名して生成物となり、用途として用いる。
芳香族アミン
芳香族アミン
ベンゼン環の原子に直接官能基が結合した化合物を分類名という。
芳香族アミンの化合物は、色の状態で、水に溶けやすさ。液性を示し、酸と反応を示し、塩となる。
アニリンの製法は、化合物に金属または金属と酸を加えて還元し塩とし、これに溶液を加えて弱塩基の反応より生成物が得られる。
検出反応は、試薬で色に呈色する。
硫酸酸性の試薬を加えると色の生成物が沈殿する。また、アニリンに試薬を加えて反応すると、結合をもつ生成物となる。
アゾ化合物の性質
アニリンC₆H₅NH₂を冷やしながら酸と試薬を反応させると、反応して生成物が得られる。
塩化ベンゼンジアゾニウム水溶液に溶液を加えると、反応が起こり、色の生成物が生成する。これは、官能基をもつ分類名であり、用途として用いる。
また、物質名を温めると反応が起こり、生成物が得られる。
芳香族化合物の分離
有機化合物の分離
有機化合物は有機溶媒などの分類名に溶けやすさ、水に溶けやすさ。また、反応によって得られる塩は水に溶けやすさ、有機溶媒に溶けやすさ。さらに、弱酸の塩に強い酸を加えると、弱酸が用語して強い酸の物質ができる。
これより、化合物、化合物、化合物、化合物が入ったジエチルエーテル溶液に希塩酸HClを加えると、液性の化合物が塩となり水層に溶けて分離できる。
次に、炭酸水素ナトリウムNaHCO₃水溶液を加えると、炭酸より強弱酸である化合物が塩となり水層に溶けて分離できる。このとき、化合物は炭酸より強弱酸であるのでエーテル層に残る。
次に、水酸化ナトリウム水溶液を加えると、液性の化合物が塩となり水層に溶けて分離できる。エーテル層に残ったのが化合物となる。
【参考】有機化合物と人間生活
耳たこ音読まとめ|高分子化合物
■ 音声プレイヤー※音が出ます!
有機化学|高分子化合物の分野の音声ファイルをまとめたものです。「高分子化合物と糖類」から「天然ゴムと合成ゴム」までの音声が流れます。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
有機化学|高分子化合物の分野の音声ファイルをまとめたものです。「高分子化合物と糖類」から「天然ゴムと合成ゴム」までの音声が流れます。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
高分子化合物と糖類
高分子化合物の基本
高分子化合物は用語が多数結びついて生じる用語であり、重合体のくり返しの構成単位数を用語という。分子量は用語で表し、約1000以上で、決まった用語がない、加熱で軟化や性質する。分類と、分類に分けられる。
重合には、炭素間に結合をもつ分子が次々と反応する反応名、分子間で分子などがとれて多数結合する反応名などがある。
単糖の性質
一般式式で表される化合物を分類名といい、別名とも呼ばれる。
分類名は、それ以上反応されない糖類の最小単位であり、酵素の作用で生成物と生成物に分解される。これを反応名という。
炭素数が5のものを分類名といい、化合物などがある。
炭素数が6のものを分類名といい、単糖は別名とも呼ばれ、水に溶けると異性体と異性体と構造の状態になる。
単糖は別名とも呼ばれ、水に溶けると構造や構造の構造と構造の状態になる。
単糖はグルコースと異性体の関係である。
単糖と単糖は分類名とよばれ、構造を形成でき、官能基をもつため○○性を示す。
また、単糖は分類名とよばれ、○○性を示す構造をもつ。
二糖の性質
単糖2分子が反応名したものを分類名といい、この結合を結合という。一般式は式となる。
二糖は別名とも呼ばれ、異性体2分子が反応名した構造を持つ。また、物質を酵素の酵素で加水分解することでも得られる。構造があり、○○性を示す。酵素の酵素で加水分解されて、生成物となる。
二糖は別名とも呼ばれ、異性体と化合物が反応名した構造をしている。○○性はないが、酵素の酵素で加水分解されて、生成物と生成物になり、これを用語といい、○○性を示すようになる。
二糖は異性体2分子が反応名した構造を持つ。また、物質を酵素の酵素で加水分解することでも得られる。構造があり、○○性を示す。酵素の酵素で加水分解されて、生成物となる。
二糖は別名とも呼ばれ、化合物と化合物が反応名した構造をしている。構造があり、○○性を示す。酵素の酵素で加水分解されて、生成物と生成物となる。
多糖の性質
分類名は、多数の分類名が結合したものをいう。
多糖は、多数の構成が反応名した構造で、多数の結合を持つ。分子式は式である。デンプンには、水に溶ける構造で構造の分類名と、熱水に溶けにくい枝分かれした構造の分類名がある。どちらも反応で色に呈色する。また、酵素の酵素を加えると、加水分解されて生成物となり、さらに加水分解すると生成物となる。
多糖とは別名ともいい、アミロペクチンより構造が多い。反応で色に呈色する。
多糖は、多数の構成が反応名した構造で、結合を持つ。分子式は式であり、分子量が大きく、分子間の結合が強く、物質にも溶けにくい。また、○○状の結合した構造をしており、ヨウ素デンプン反応を示さない。酵素の酵素を加えると、加水分解されて生成物となる。物質に酸と酸の混合物(用語)を作用させると、分類名である生成物が得られる。
セルロースと繊維
セルロースを試薬で反応して生成物とする。これを反応すると生成物が得られ、これを繊維名といい、分類名である。
また分類は、セルロースを試薬で溶かして再生した繊維の繊維名と、セルロースを溶液と試薬を用いて中間体にしたあと、再生した繊維の繊維名がある。繊維名の形状のものが用語である。
アミノ酸とタンパク質
アミノ酸の性質
分類名は、同一の炭素原子に官能基と官能基を結合した化合物で、物質を加水分解して得られ、約数種類ある。グリシン以外は用語をもち、異性体が存在する。また、体内でつくられないアミノ酸を用語という。
アミノ酸の種類は、アミノ酸やアミノ酸、ヒドロキシ基をもつアミノ酸、硫黄を含むアミノ酸やアミノ酸、ベンゼン環をもつアミノ酸やアミノ酸がある。また、酸性のアミノ酸にはアミノ酸があり、塩基性のアミノ酸にはアミノ酸がある。
アミノ酸の反応
アミノ酸は色と状態で、水に溶けやすさが、物質には溶けにくい。
アミノ酸は、液性溶液中では陽イオンが多くなり、液性溶液中では陰イオンが多くなる。また、溶液中の条件となる pH を用語といい、このときアミノ酸はイオンの割合が最も多くなる。
グルタミン酸は官能基を2つもつので、用語が液性側に寄る。また、リシンは官能基を2つもつので、用語が液性側に寄る。
アミノ酸に物質を加えると、官能基が反応して反応する。また、試薬を加えると、官能基が反応して反応する。
試薬を加えて温めると、色に呈色する。これを反応名といい、アミノ酸の検出に用いる。
タンパク質の性質
アミノ酸2分子の官能基と官能基が反応名して結合をつくり、用語となる。アミノ酸3分子が結合したものを用語といい、多数のアミノ酸が結合したものを用語という。
分類名の構造は、用語の配列順序を構造段階といい、結合間の結合によるらせん状の二次構造やジグザグ状の二次構造を構造段階という。
二次構造がさらに結合などによって形成される立体構造を構造段階といい、三次構造が複数集まって形成される立体構造を構造段階という。
タンパク質は、分類名だけからなる分類と、分類名以外に糖やリン酸、色素、核酸なども含む分類名に分類できる。
また、形状によって、ポリペプチド鎖が複雑に球状になる分類名と、束になった分類名に分類される。
タンパク質の反応
タンパク質は、条件や条件、要因、要因などで立体的な構造が変化し、現象や現象が起こる。これをタンパク質の用語という。
結合を2つ以上含むタンパク質に、試薬と少量の試薬を加えると、色になる。これを反応名という。
構造を含むタンパク質に試薬を加えて加熱すると、色になり、冷却後試薬を加えて液性にすると色になる。これを反応名という。
官能基を含むタンパク質に試薬を加えて加熱すると、色に呈色する。これを反応名という。
元素を含むタンパク質に試薬を加えて加熱し、試薬を加えると、生成物の色沈殿が生じる。
元素を含むタンパク質に試薬を加えて加熱すると、生成物が発生して試験紙が色になる。
酵素と核酸
酵素の性質
用語は生体内の化学反応で用語としてはたらく分類名である。酵素が働く物質を用語といい、酵素と用語に結合して反応するため、酵素には用語という用語をもつ。
酵素によって用語は決まっており、それ以外では作用しない。これを用語という。また、酵素によって生成する物質が決まっており、これを用語という。
酵素の多くは温度前後で最も働く用語となり、低温では機能が低下する。また、高温では用語して触媒作用を失い、これを用語という。さらに、酵素が最も働くpHを用語といい、酵素の種類によって異なる。
核酸の性質
リン酸、糖、塩基からなる構成単位が反応名してできる用語を分類名といい、核酸と核酸がある。
DNA(デオキシリボ核酸)は、成分と五炭糖の糖、塩基の塩基、塩基、塩基、塩基からなる。
DNAは、形質を伝える用語の本体で、その構造は2本の構造が塩基の間で結合をつくり、構造となる。
RNA(リボ核酸)は、成分と五炭糖の糖、塩基の塩基、塩基、塩基、塩基からなる。
【参考】高分子化合物の分類
天然繊維と合成繊維
繊維の分類
繊維には分類名と分類名がある。
天然繊維には、主成分を主成分とする例や例などの分類名と、主成分を主成分とする例や例などの分類名がある。
化学繊維には、天然繊維などの天然繊維を溶液にして再び繊維状にする分類名と、天然繊維などの天然繊維を操作する分類名、重合体などの重合体からなる分類名の分類名がある。
合成繊維の種類
反応名による合成繊維には、分類名として、2価カルボン酸の化合物と、2価アルコールの化合物の反応名によって得られる、合成繊維などがある。
また、分類名として、ジカルボン酸の化合物とジアミンの化合物の反応名で得られる合成繊維、モノマーを重合すると得られる合成繊維などがある。
付加重合による合成繊維には、分類名があり、モノマーの付加重合で得られる合成繊維、モノマーの付加重合で得られる合成繊維、モノマーの付加重合で得られる合成繊維がある。また、モノマーとモノマーやモノマーを重合させた合成繊維がある。
モノマーを付加重合して高分子をつくり、これを反応名して高分子を合成する。これに化合物で処理して○○化すると合成繊維が得られる。
合成樹脂
合成樹脂の性質
合成樹脂の種類で、用語するとやわらかくなり、冷やすと再び用語するものを分類名といい、用語すると硬化して再びやわらかくならないものを分類名という。
熱可塑性樹脂の種類には、モノマーの付加重合で得られる高分子、モノマーの付加重合で得られる高分子、モノマーの付加重合で得られる高分子、モノマーの付加重合で得られる高分子、モノマーの付加重合で得られる高分子、モノマーの付加重合で得られる高分子などがある。また、高分子、高分子や高分子も熱可塑性樹脂である。
熱硬化性樹脂の種類には、化合物と化合物との付加縮合で得られる高分子や、化合物と化合物との付加縮合で得られる高分子、化合物と化合物との付加縮合で得られる高分子があり、尿素樹脂とメラミン樹脂は分類名と呼ばれる。また、化合物と化合物との縮合重合で得られる高分子、化合物などの縮合重合で得られる高分子などがある。
フェノール樹脂は、化合物と溶液を加熱するとき、触媒を用いるときは中間生成物の中間体を、触媒を用いるときは中間体を経由して得られる。また、フェノール樹脂は、構造が構造要素で結合する構造をしている。
イオン交換樹脂の性質
モノマーとモノマーを重合させた用語の樹脂に、酸を作用させて官能基をつけた樹脂を用語といい、水溶液中のイオンとイオンが交換される。
また、共重合体の樹脂に塩基性の基をつけた樹脂を用語といい、水溶液中のイオンとイオンが交換される。
この2つのイオン交換樹脂に同時に水溶液を通すと、イオンを含まない用語となる。
また、効力がなくなった陽イオン交換樹脂は再生剤を加えると再生し、陰イオン交換樹脂は再生剤を加えると再生する。
このようなイオン交換樹脂を用語という。
機能性樹脂の種類
その他の機能性樹脂には、ポリアセチレンの誘導体で、金属に近い性質をもつ分類やアクリル酸ナトリウムの重合体からなり、多量の物質を性質することができる分類。また、ポリ乳酸などの要因によって分解されやすい分類や要因によって硬化する分類がある。
天然ゴムと合成ゴム
天然ゴムの性質
ゴムの木から取れる物質を操作したものを用語といい、主成分はモノマーが付加重合した高分子である。また、結合が配置であるため、○○力がある。
天然ゴムに数%の物質を加えて加熱することを用語といい、硫黄原子による構造が形成される。これにより、○○力などが向上する。また、30〜40%の硫黄で用語を行うと、硬い用語となる。
合成ゴムの性質
合成ゴムの種類には、モノマーに似た単量体であるモノマーの付加重合で得られる高分子や、モノマーの付加重合で得られる高分子がある。
また、モノマーとモノマーの重合で得られる高分子や、モノマーとモノマーの重合で得られる高分子もあり、ジクロロジメチルシランから合成される高分子などがある。
有機化合物の反応経路図