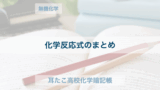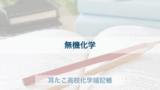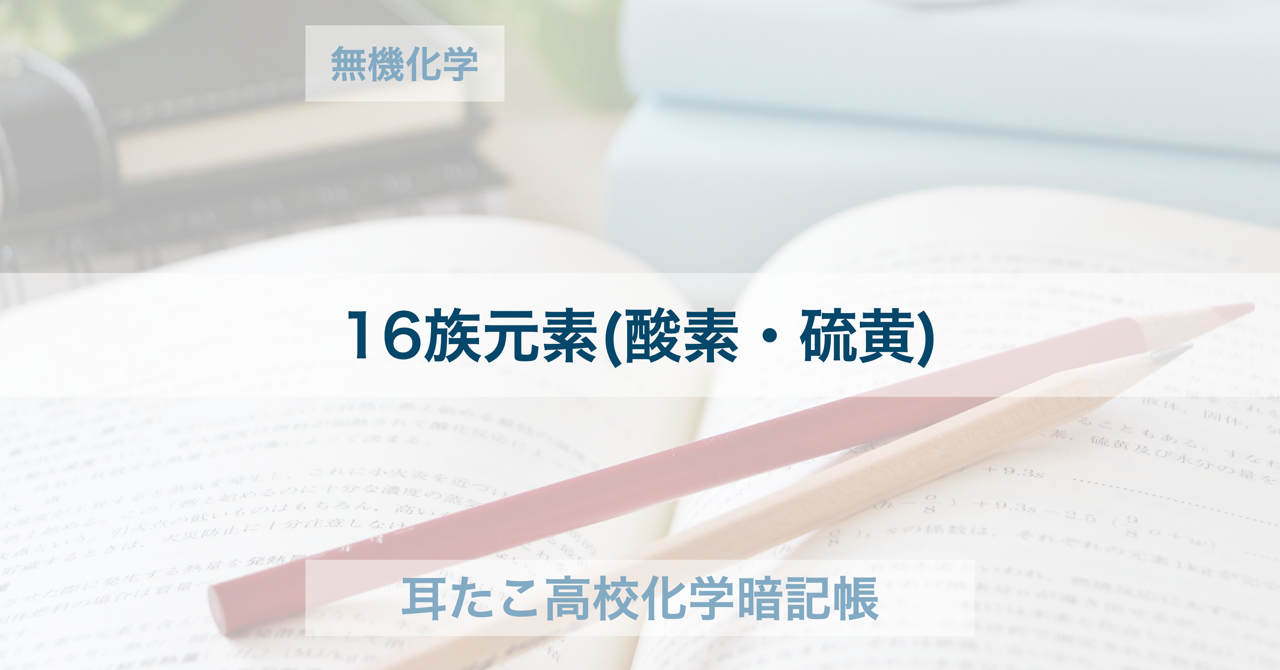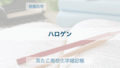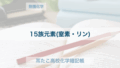- 耳たこ無機化学「16族元素(酸素・硫黄)」の暗記ページです。
- 四角い枠をクリックすると解答が表示され、下のボタンで一括表示・非表示の切替ができます。
- 耳たこ音読では音声ファイルを再生して要点を音読します。通学時間などのスキマ学習に最適です。
- 目次をクリックすると各セクションへ移動します。
16族元素(酸素)
耳たこ音読|酸素の性質
音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
数族元素の酸素の同素体には、色・臭い・毒性の気体で空気中の約数%を占める同素体と、色・臭い・毒性な気体である同素体がある。オゾンは○○作用が強く、ヨウ化カリウムデンプン紙を色にする。
酸素の実験室的製法は、化合物に触媒として触媒を加えるか、化合物に触媒として触媒を加えて加熱することで得られる。また、工業的製法は物質の用語で得られる。
オゾンは酸素に用語するか、酸素に用語を当てることで得られる。
酸素の同素体
化学式
色・状態
臭い・毒
化学式
色・状態
臭い・毒
■ 酸素O₂の性質
② 空気中の約数%を占有。
③用語して用語を得る。
□ 酸素O₂の実験室的製法
①物質名に触媒として物質名を加える。
(式) 2H₂O₂ → 2H₂O + O₂
②物質名に触媒として物質名を加えて加熱。
(式) 2KClO₃ → 2KCl + 3O₂
③ 工業的製法は物質名の方法で得られる。
■ オゾンO₃の性質
□ オゾンO₃の実験室的製法
① 酸素中で方法。
(式) 3O₂ → 2O₃
② 酸素に用語をあてる。
酸化物の分類
分類名
例:CO₂、NO₂、P₄O₁₀、SO₂
分類名
例:Na₂O、K₂O、MgO、CaO
分類名
例:Al₂O₃、ZnO
オキソ酸
16族元素(硫黄)
耳たこ音読|硫黄の同素体
音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
数族元素の硫黄の同素体には、色で形状の安定している同素体、色で形状の同素体、○○力があり色の同素体がある。
耳たこ音読|硫化水素と二酸化硫黄
音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
硫黄の化合物は、色・臭い・毒性の状態で、水溶液は価数と液性を示す。硫化水素の製法は、化合物に酸または酸を加えることで得られる。
硫黄の化合物は、色・臭い・毒性の状態で、水溶液は価数と液性を示す。○○作用が強く○○作用があるが、硫化水素はより強い還元作用を持つため、二酸化硫黄は○○剤として働く。二酸化硫黄の製法は、金属に酸を加えて加熱するか、化合物に酸を加えることで得られる。
耳たこ音読|硫酸の性質
音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
酸の工業的製法は、製法名という。原料を燃焼して化合物を得る。これを触媒を触媒として酸化すると、化合物となる。さらに、酸に吸収させて水と反応させると、硫酸が得られる。
酸は性質の酸で、性質の酸の塩と加熱すると揮発性の酸が遊離する。○○性が強く、○○剤として用いる。○○作用があり、スクロースを用語して色に変色させる。用語が大きいため、薄めるときは物質に濃硫酸を加える。
酸は強い○○作用があり、金属や金属とも反応する。
酸は液性であり、イオン化傾向の大きい金属と反応して気体を発生する。
硫黄の同素体
同素体S₈
同素体S₈
色で形状の同素体。
同素体
硫化水素と二酸化硫黄
化学式
色・状態
臭い・毒性
価数の液性
化学式
色・状態
臭い・毒性
価数の液性
■ 硫化水素H₂Sの性質
② 強い○○作用がある。
(式) H₂S + I₂ → S + 2HI
□ 硫化水素H₂Sの実験室的製法
①物質名に物質名(酸)を加える。
(式) FeS + H₂SO₄ → FeSO₄ + H₂S
②物質名に物質名(酸)を加える。
(式) FeS + 2HCl → FeCl₂ + H₂S
■ 二酸化硫黄SO₂の性質
②○○作用がある。
(式) SO₂ + I₂ + 2H₂O → H₂SO₄ + 2HI
物質名に対しては○○剤として働く。
(式) SO₂ + 2H₂S → 3S + 2H₂O
□ 二酸化硫黄SO₂の実験室的製法
① 金属に物質名(酸)を加えて加熱。
(式) Cu + 2H₂SO₄ → CuSO₄ + 2H₂O + SO₂
② 物質名に物質名(酸)を加える。
(式) Na₂SO₃ + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + H₂O + SO₂
③ 物質名に物質名(酸)を加える。
(式) 2NaHSO₃ + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + 2H₂O + 2SO₂
硫酸の製法(接触法)
(式) S + O₂ → SO₂
② これを物質名を触媒として用語させて物質名とする。
(式) 2SO₂ + O₂ → 2SO₃
③ これを物質名に吸収させて物質名と反応すると物質名となる。
(式) SO₃ + H₂O → H₂SO₄
④ これに物質名を加えて薄める。
濃硫酸と希硫酸
化学式
密度が高低
○性のある状態
色・臭い
化学式
状態
色・臭い
液性の強弱
■ 濃硫酸の性質
(式) NaCl + H₂SO₄ → NaHSO₄ + HCl
② ○○性が強く、○○剤に用いる。
③ ○○作用があり、用語内の水素Hと酸素Oを奪う。
→用語を用語して黒色に変色。
④ 物質名は強い○○作用があり、銅Cuや銀Agとも反応。
(式) Cu + 2H₂SO₄ → CuSO₄ + 2H₂O + SO₂
■ 希硫酸の性質
② 硫酸塩の性質は、
Na₂SO₄、MgSO₄ → 水に溶けやすさ
CaSO₄、Pb₂SO₄ → 水に溶けやすさ
□ 希硫酸の製法
水に物質名を加えると用語を発生するので、大量の物質名の中に物質名を加えて薄める。
化学反応式演習|酸素と硫黄の反応
この単元の化学反応式の演習問題です。
[ 解答と解説を見る ]をクリックすると解答と解説が表示されます。
12 過酸化水素水と酸化マンガン(Ⅳ)
過酸化水素水に触媒として酸化マンガン(Ⅳ)を加える反応。
[ 解答と解説を見る ]
酸素の実験室的製法で、酸素が発生する。
2H₂O₂ → 2H₂O + O₂ ( 触媒 MnO₂ )
13 塩素酸カリウムと酸化マンガン(Ⅳ)で加熱
塩素酸カリウムに触媒として酸化マンガン(Ⅳ)を加えて加熱する反応。
[ 解答と解説を見る ]
酸素の実験室的製法で、酸素が発生する。
2KClO₃ → 2KCl + 3O₂ ( 触媒 MnO₂ )
14 酸素中で放電
酸素中で放電する。
[ 解答と解説を見る ]
オゾンが発生する。
3O₂ → 2O₃
15 硫化水素と二酸化硫黄
硫化水素と二酸化硫黄を反応させる。
[ 解答と解説を見る ]
硫化水素は還元剤、二酸化硫黄は酸化剤として働く。
SO₂ + 2H₂S → 3S + 2H₂O
16 硫化鉄(Ⅱ)と希硫酸
硫化鉄(Ⅱ)に希硫酸を加える反応。
[ 解答と解説を見る ]
硫化水素が発生する。
FeS + H₂SO₄ → FeSO₄ + H₂S
弱酸の硫化水素の遊離反応。
17 硫化鉄(Ⅱ)と希塩酸
硫化鉄(Ⅱ)に希塩酸を加える反応。
[ 解答と解説を見る ]
硫化水素が発生する。
FeS + 2HCl → FeCl₂ + H₂S
弱酸の硫化水素の遊離反応。
18 銅と濃硫酸で加熱
銅に濃硫酸を加えて加熱する反応。
[ 解答と解説を見る ]
二酸化硫黄が発生する。
Cu + 2H₂SO₄ → CuSO₄ + 2H₂O + SO₂
熱濃硫酸は強い酸化作用がある。
19 亜硫酸ナトリウムと希硫酸
亜硫酸ナトリウムに希硫酸を加える反応。
[ 解答と解説を見る ]
二酸化硫黄が発生する。
Na₂SO₃ + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + H₂O + SO₂
20 亜硫酸水素ナトリウムと希硫酸
亜硫酸水素ナトリウムに希硫酸を加える反応。
[ 解答と解説を見る ]
二酸化硫黄が発生する。
2NaHSO₃ + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + 2H₂O + 2SO₂
21 接触法
接触法の3つの反応式。
[ 解答と解説を見る ]
① 硫黄を燃焼して二酸化硫黄とする。
S + O₂ → SO₂
② 二酸化硫黄を酸化バナジウムを触媒として酸化させて、三酸化硫黄とする。
2SO₂ + O₂ → 2SO₃
③ 三酸化硫黄を濃硫酸に吸収させて、水と反応させて発煙硫酸とする。
SO₃ + H₂O → H₂SO₄
④ 希硫酸を加えて薄める。