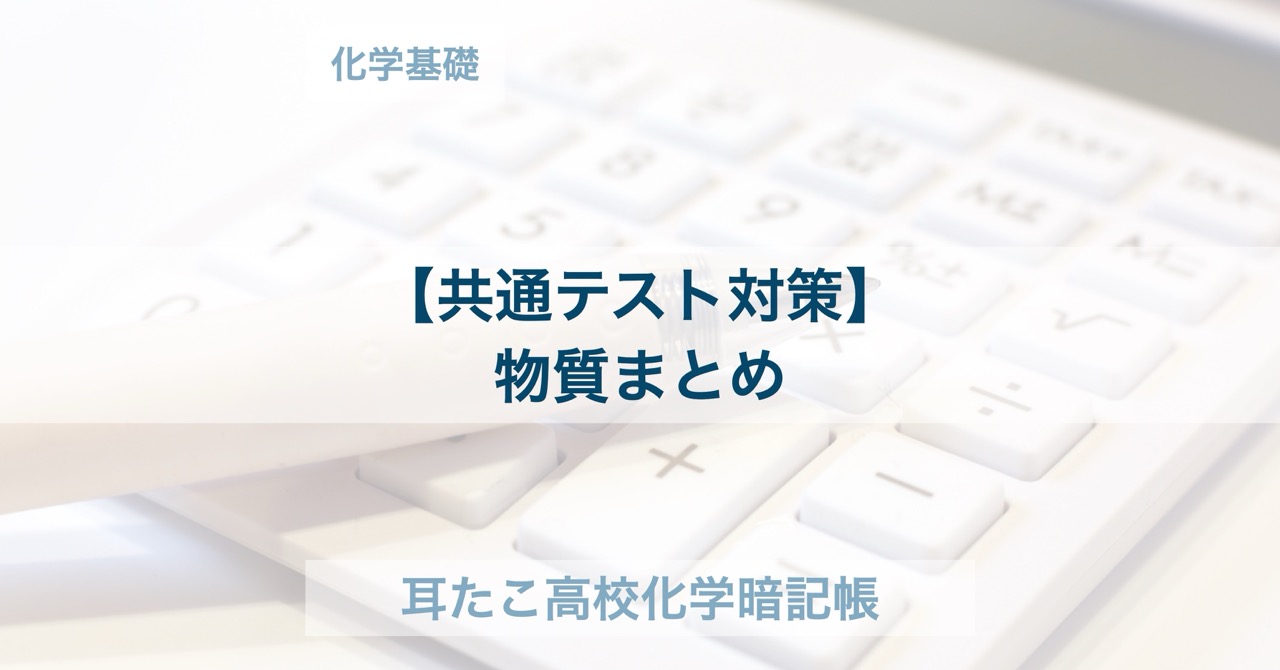- 耳たこ化学基礎「【共通テスト対策】物質まとめ」の暗記ページです。
- 共通テストの化学基礎分野の頻出物質の性質をまとめています。
- 四角い枠をクリックすると解答が表示され、下のボタンで一括表示・非表示の切替ができます。
- 耳たこ音読では音声ファイルを再生して要点を音読します。通学時間などのスキマ学習に最適です。
- 目次をクリックすると各セクションへ移動します。
非金属元素の単体と化合物
耳たこ音読|非金属元素の単体と化合物①
音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
水素H₂は、分子の形で極性or無極性である。製法は、金属に酸を加えると発生する。燃やすと生成物が生成する。水素イオンH⁺は価数のイオンの種類である。
酸素O₂は、同素体に同素体がある。製法は、化合物に化合物を加えると発生する。物を現象させる働きがある。酸化物イオンO²⁻は価数のイオンの種類である。
窒素N₂は、分子の形で極性or無極性である。空気中に約体積比含む。
炭素Cには、同素体として結晶の種類で硬く電気を通さない同素体、やわらかく電気を通しやすい同素体、球状分子の同素体、筒状の同素体がある。
硫黄Sには、同素体として同素体、同素体、同素体がある。
リンPには、同素体として猛毒で性質するので水中に保存する同素体と、安定している同素体がある。
フッ素F₂は、分類名で1価の陰イオンのイオン名になりやすく、単体は分子の種類である。用語は最大である。
塩素Cl₂は、分類名で1価の陰イオンのイオン名になりやすく、単体は分子の種類であり、○○剤として働く。
臭素Br₂は、分類名で1価の陰イオンのイオン名になりやすく、単体は分子の種類であり、○○剤として働く。
ヨウ素I₂は、分類名で1価の陰イオンのイオン名になりやすく、単体は分子の種類で、結晶の種類となり、○○性がある。○○剤として働く。
ヘリウムHeは、分類名で価電子が数値でイオンや化合物になりにくく、単体は分子の種類である。最外殻電子数は数値で、用語が最大である。
ネオンNeは、分類名で価電子が数値でイオンや化合物になりにくく、単体は分子の種類である。最外殻電子数は数値である。
アルゴンArは、分類名で価電子が数値でイオンや化合物になりにくく、単体は分子の種類である。最外殻電子数は数値である。
耳たこ音読|非金属元素の単体と化合物②
音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
水H₂Oは、分類の化合物で分子の形の極性or無極性である。電気分解では陽極に気体、陰極に気体が発生する。水は水素イオンH⁺と結合して安定したイオン名となる。反応名では酸のH⁺と塩基のOH⁻から水H₂Oが生成する。
塩化水素HClは、分子の形だが用語の差により極性or無極性である。水溶液は酸で価数と強さである。金属との反応は、イオン化傾向の金属〜金属と反応して気体を発生する。電気分解では陽極に気体、陰極に気体が発生する。
硝酸HNO₃は、価数と強さである。金属との反応は、イオン化傾向の金属〜金属と反応し、金属や金属とは反応しない。
硫酸H₂SO₄は、価数と強さである。物質は金属〜金属と反応して気体を発生する。物質は金属〜金属と反応し、金属や金属とは反応しない。
シュウ酸H₂C₂O₄は、価数と強さである。○○剤として働く。
リン酸H₃PO₄は、価数と強さである。イオン名は3価の陰イオンである。
酢酸CH₃COOHは、価数と強さである。
二酸化炭素CO₂は、物質(別名)に酸を加えると発生し、試薬を白く濁らせる。分子の形で、極性or無極性である。固体の固体名は結晶の種類で、やわらかくもろく、融点は低く、電気を通しにくい。
アンモニアNH₃は、物質に物質を加えると発生する。臭いがあり、水に溶けやすさて、価数と強さとなる。アンモニアは水素イオンH⁺と結合し、安定したイオン名となる。
メタンCH₄は、分子の形の極性or無極性である。
過酸化水素H₂O₂は、○○剤として働くが、酸化剤や酸化剤に対しては○○剤として働く。物質に過酸化水素水を加えると気体が発生する。
二酸化硫黄SO₂は、還元剤であるが、化合物に対しては○○剤として働く。
硫化水素H₂Sは、○○剤である。
ケイ素Siは、結晶の種類で、融点は非常に高く、電気を通さず、水に溶けない。性質の性質を示し、分類ではない。
二酸化ケイ素SiO₂は、結晶の種類で、融点は非常に高く、電気を通さず、水に溶けない。
水素 H₂
製法は、金属に酸を加えると発生する。
燃やすと生成物が生成する。
2H₂ + O₂ → 2H₂O
イオン名は価数のイオンの種類である。
酸と塩基の人物の定義で、酸は水溶液中でイオン名を出す物質であり、人物の定義では酸はイオン名を与える物質である。
反応名では、酸のイオン名と塩基のイオン名から生成物が生成し、同時に生成物が生成する。
酸化と還元の定義で、酸化は水素Hを用語反応であり、還元は水素Hを用語反応である。
酸化数の扱いでは、化合物中の水素Hは酸化数であるが、例外として水素化ナトリウムNaHのHは酸化数となる。
酸素 O₂
製法は、化合物に化合物を加えると発生する。
物を現象させる働きがある。
イオン名は価数のイオンの種類。
酸化と還元の定義において、酸化は酸素Oを用語反応であり、還元は酸素Oを用語変化である。
酸化数の扱いでは、化合物中の酸素Oは通常 酸化数。ただし、化合物中の酸素Oは 酸化数となる。
窒素 N₂
空気中に約体積比含む。
炭素 C
硫黄 S
リン P
フッ素 F₂
用語は最大となる。
原子の電子配置は電子配置となる。
イオン名は価数のイオンの種類。
塩素 Cl₂
○○剤としてはたらく。
Cl₂ + H₂ → 2HCl
Cl₂ + 2HI → 2HCl + I₂
イオン名は価数のイオンの種類。
臭素 Br₂
○○剤としてはたらく。
Br₂ + SO₂ + 2H₂O → H₂SO₄ + 2HBr
イオン名は価数のイオンの種類。
ヨウ素 I₂
○○剤としてはたらく。
I₂ + H₂S → 2HI + S
イオン名は価数のイオンの種類。
ヘリウム He
最外殻電子数は数値で、電子配置は電子配置となる。
用語が最大となる。
ネオン Ne
最外殻電子数は数値で、電子配置は電子配置となる。
アルゴン Ar
最外殻電子数は数値で、電子配置は電子配置となる。
水 H₂O
電気分解すると陽極側に気体、陰極側に気体が発生する
水H₂Oがイオン名と結合し、安定したイオン名となる。
反応名では、酸のH⁺と塩基のOH⁻から生成物が生成する。
塩化水素 HCl
水溶液は酸で、価数と強さである。
HCl → H⁺ + Cl⁻
塩基と反応名する。
HCl + NaOH → NaCl + H₂O
金属との反応は、イオン化傾向の金属〜金属と反応して気体を発生する。金属〜金属とは反応しない。
電気分解すると、陽極に気体、陰極に気体が発生する。
硝酸 HNO₃
HNO₃ → H⁺ + NO₃⁻
塩基と反応名する。
HNO₃ + NaOH → NaNO₃ + H₂O
金属との反応は、イオン化傾向の金属〜金属と反応する。金属や金属とは反応しない。
硫酸 H₂SO₄
H₂SO₄ → 2H⁺ + SO₄²⁻
塩基と反応名する。
H₂SO₄ + 2NaOH → Na₂SO₄ + 2H₂O
H₂SO₄ + Ca(OH)₂ → CaSO₄ + 2H₂O
物質と金属との反応は、イオン化傾向の金属〜金属と反応して気体を発生する。金属〜金属とは反応しない。
物質と金属との反応は、イオン化傾向の金属〜金属と反応する。金属や金属とは反応しない。
シュウ酸 H₂C₂O₄
価数と強さである。
○○剤として働く。
H₂C₂O₄ → 2CO₂ + 2H⁺ + 2e⁻
リン酸 H₃PO₄
イオン名は価数のイオンの種類である。
酢酸 CH₃COOH
CH₃COOH ⇄ H⁺ + CH₃COO⁻
塩基と反応名する。
CH₃COOH + NaOH → CH₃COONa + H₂O
塩に強酸を加えると、強酸の塩と化合物が得られる。
CH₃COONa + HCl → NaCl + CH₃COOH
二酸化炭素 CO₂
試薬を白く濁らせる。
分子は分子の形で、極性or無極性である。
固体の固体名は、結晶の種類で、やわらかくもろく、融点は低く、電気を通しにくい。
アンモニア NH₃
臭いがあり、水に溶けやすさて、価数と強さとなる。
酸と反応名する。
アンモニアNH₃がイオン名と結合し、安定したイオン名となる。
メタン CH₄
過酸化水素 H₂O₂
○○剤として働く。
H₂O₂ + 2KI + H₂SO₄
→ 2H₂O + I₂ + K₂SO₄
酸化剤や酸化剤に対しては○○剤として働く。
2KMnO₄ + 5H₂O₂ + 3H₂SO₄
→ 2MnSO₄ + 5O₂ + K₂SO₄ + 8H₂O
物質に物質を加えると気体が発生する。
二酸化硫黄 SO₂
SO₂ + Cl₂ + 2H₂O → H₂SO₄ + 2HCl
化合物に対しては○○剤として働く。
SO₂ + 2H₂S → 3S + 2H₂O
硫化水素 H₂S
2H₂S + O₂ → 2S + 2H₂O
化合物に対しては、SO₂が○○剤として働く関係にある。
2H₂S + SO₂ → 3S + 2H₂O
ケイ素 Si
性質の性質を示す。
分類ではない。
二酸化ケイ素 SiO₂
金属元素とイオン化傾向
耳たこ音読|金属元素とイオン化傾向①
音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
リチウムLiは、1族元素の分類名に分類され、イオン名は1価の陽イオンである。炎色反応は色となる。空気とは条件で速やかに反応して酸化し、水とは条件で反応して気体を発生する。酸や酸と反応して水素を発生する。
カリウムKは、1族元素の分類名に分類され、イオン名は1価の陽イオンである。炎色反応は色となる。空気とは条件で速やかに反応して酸化し、水とは条件で反応して気体を発生する。
カルシウムCaは、2族元素の分類名に分類され、イオン名は2価の陽イオンである。炎色反応は色となる。空気とは条件で速やかに反応して酸化し、水とは条件で反応して気体を発生する。酸や酸と反応して水素を発生する。
ナトリウムNaは、1族元素の分類名に分類され、イオン名は1価の陽イオンである。炎色反応は色となる。空気とは条件で速やかに反応して酸化し、水とは条件で反応して気体を発生する。酸や酸と反応して水素を発生する。
マグネシウムMgは、2族元素の分類名に分類され、イオン名は2価の陽イオンである。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは条件と反応し、酸や酸と反応して水素を発生する。
アルミニウムAlは、イオン名が3価の陽イオンであり、合金に合金がある。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは高温の条件で反応し、酸や酸と反応して、気体を発生する。ただし、濃硝酸では性質となり溶けない。
亜鉛Znは、イオン名が2価の陽イオンであり、鉄Feに亜鉛Znをめっきしたものを用語という。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは高温の条件で反応し、酸や酸と反応して、気体を発生する。
鉄Feは、2価の鉄(Ⅱ)イオンFe²⁺と3価の鉄(Ⅲ)イオンFe³⁺がある。鉄FeにスズSnをめっきしたものを用語といい、亜鉛Znをめっきしたものを用語という。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは高温の条件で反応し、酸や酸と反応して、気体を発生する。ただし、濃硝酸では性質となり溶けない。
耳たこ音読|金属元素とイオン化傾向②
音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
ニッケルNiは、空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは反応?。酸や酸と反応して、気体を発生するが、濃硝酸では性質となり溶けない。
スズSnは、鉄FeにスズSnをめっきしたものを用語という。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは反応?。酸や酸と反応して、気体を発生する。
鉛Pbは、イオン名が2価の陽イオンである。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは反応?。酸や酸を発生するが、水に溶けない膜をつくり反応?。
銅Cuは、イオン名が2価の陽イオンであり、炎色反応は色である。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは反応?。酸や酸とは反応する。
水銀Hgは、常温で状態である。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置しても反応?、水とも反応?が、酸や酸とは反応する。
銀Agは、イオン名が1価の陽イオンである。空気とは常温で放置しても反応?、水とも反応?。酸や酸とは反応する。
白金Ptは、空気とは常温で放置しても反応?、水とも反応?。王水には溶ける。
金Auは、空気とは常温で放置しても反応?、水とも反応?。王水には溶ける。
ストロンチウムSrは、2族元素で分類名に分類され、炎色反応は色となる。
バリウムBaは、2族元素で分類名に分類され、炎色反応は色となる。
リチウム Li
イオン名は、価数のイオン種である。
炎色反応は色である。
・イオン化列
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、条件で速やかに反応して酸化する。
水とは、条件で反応して気体を発生する。
酸や酸とも反応して、気体を発生する。
カリウム K
イオン名は、価数のイオン種である。
炎色反応は色である。
・イオン化列
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、条件で速やかに反応して酸化する。
水とは、条件で反応して気体を発生する。
酸や酸とも反応して、気体を発生する。
カルシウム Ca
イオン名は、価数のイオン種である。
炎色反応は色である。
・イオン化列
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、条件で速やかに反応して酸化する。
水とは、条件で反応して気体を発生する。
酸や酸とも反応して、気体を発生する。
ナトリウム Na
イオン名は、価数のイオン種である。
炎色反応は色である。
・イオン化列
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、条件で速やかに反応して酸化する。
水とは、条件で反応して気体を発生する。
酸や酸とも反応して、気体を発生する。
マグネシウム Mg
イオン名は、価数のイオン種である。
・イオン化列
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、条件により反応して酸化する。
常温で放置すると、用語をつくる。
水とは、条件と反応する。
酸や酸とも反応して、気体を発生する。
アルミニウム Al
合金に合金がある。
・イオン化列
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、条件により反応して酸化する。
常温で放置すると、用語をつくる。
水とは、高温の条件で反応する。
酸や酸とも反応して、気体を発生する。ただし、酸では性質となり溶けない。
亜鉛 Zn
金属に亜鉛Znをめっきしたものを用語という。
・イオン化列
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、条件により反応して酸化する。
常温で放置すると、用語をつくる。
水とは、高温の条件で反応する。
酸や酸とも反応して、気体を発生する。
鉄 Fe
鉄Feに元素をめっきしたものを用語という。
鉄Feに元素をめっきしたものを用語という。
・イオン化列
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、条件により反応して酸化する。
常温で放置すると、用語をつくる。
水とは、高温の条件で反応する。
酸や酸とも反応して、気体を発生する。ただし、酸では性質となり溶けない。
ニッケル Ni
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、条件により反応して酸化する。
常温で放置すると、用語をつくる。
水とは、反応?。
酸や酸とも反応して、気体を発生する。ただし、酸では性質となり溶けない。
スズ Sn
・イオン化列
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、条件により反応して酸化する。
常温で放置すると、用語をつくる。
水とは、反応?。
酸や酸とも反応して、気体を発生する。
鉛 Pb
・イオン化列
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、条件により反応して酸化する。
常温で放置すると、用語をつくる。
水とは、反応?。
酸や酸とも反応して、気体を発生する。ただし、水に溶けない膜をつくり反応?。
銅 Cu
炎色反応は色である。
・イオン化列
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、条件により反応して酸化する。
常温で放置すると、用語をつくる。
水とは、反応?。
酸や酸と反応する。(酸や酸とは反応しない。)
水銀 Hg
・イオン化列
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、条件により反応して酸化する。
常温で放置しても反応?。
水とは、反応?。
酸や酸と反応する。(酸や酸とは反応しない。)
銀Ag
・イオン化列
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、常温で放置しても反応?。
水とは、反応?。
酸や酸と反応する。(酸や酸とは反応しない。)
白金 Pt
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、常温で放置しても反応?。
水とは、反応?。
混酸に溶ける。
金 Au
Ni Sn Pb H₂ Cu Hg Ag Pt Au
空気とは、常温で放置しても反応?。
水とは、反応?。
混酸に溶ける。
ストロンチウム Sr
炎色反応は色となる。
バリウム Ba
炎色反応は色となる。
イオン結合の化合物
耳たこ音読|イオン結合の化合物
音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
水酸化ナトリウムNaOHは、価数と強さで酸と中和反応する。
水酸化カリウムKOHは、価数と強さで酸と中和反応する。
水酸化カルシウムCa(OH)₂は、価数と強さで酸と中和反応する。
水酸化マグネシウムMg(OH)₂は、価数と強さで酸と中和反応する。
水酸化銅(Ⅱ)Cu(OH)₂は、価数と強さで酸と中和反応する。
塩化ナトリウムNaClは、結合している結晶で、塩の分類である。塩酸HClと水酸化ナトリウムNaOHなどの反応名で、生成物として得られる。
炭酸水素ナトリウムNaHCO₃は、塩の分類であり、酸の強さと塩基の強さの塩であるので、水溶液は液性である。炭酸水素ナトリウムNaHCO₃に強酸を加えると、強酸の塩の強酸の塩が得られる。また、熱分解で生成物が得られる。
硫酸水素ナトリウムNaHSO₄は、塩の分類である。酸の強さと塩基の強さの塩であるが、電離できるH⁺をもつため水溶液は液性を示す。
炭酸カルシウムCaCO₃は、別名ともいわれ、酸の強さと塩基の強さの塩であるので、水溶液は液性である。炭酸カルシウムに酸を加えると、強酸の塩の強酸の塩が得られる。これは、気体の製法でもある。
過マンガン酸カリウムKMnO₄は、○○剤であり、反応前後で色から色となる。実験では指示薬なしで滴定できる。
二クロム酸カリウムK₂Cr₂O₇は、○○剤であり、反応前後で色から色となる。
酸化銅(Ⅱ)CuOは○○剤として働き、金属となる。
ヨウ化カリウムKIは○○剤として働き、単体となる。
水酸化ナトリウム NaOH
NaOH → Na⁺ + OH⁻
中和反応では、酸のイオン名と反応して生成物が生成し、同時に生成物が生成する。
HCl + NaOH → NaCl + H₂O
H₂SO₄ + 2NaOH → Na₂SO₄ + 2H₂O
水酸化カリウム KOH
KOH → K⁺ + OH⁻
中和反応では、酸のイオン名と反応して生成物が生成し、同時に生成物が生成する。
HCl + KaOH → KCl + H₂O
H₂SO₄ + 2KOH → K₂SO₄ + 2H₂O
水酸化カルシウム Ca(OH)₂
Ca(OH)₂ → Ca²⁺ + 2OH⁻
中和反応では、酸のイオン名と反応して生成物が生成し、同時に生成物が生成する。
2HCl + Ca(OH)₂ → CaCl₂ + 2H₂O
H₂SO₄ + Ca(OH)₂ → CaSO₄ + 2H₂O
水酸化マグネシウム Mg(OH)₂
中和反応では、酸のイオン名と反応して生成物が生成し、同時に生成物が生成する。
2HCl + Mg(OH)₂ → MgCl₂ + 2H₂O
H₂SO₄ + Mg(OH)₂ → MgSO₄ + 2H₂O
水酸化銅(Ⅱ) Cu(OH)₂
中和反応では、酸のイオン名と反応して生成物が生成し、同時に生成物が生成する。
2HCl + Cu(OH)₂ → CuCl₂ + 2H₂O
H₂SO₄ + Cu(OH)₂ → CuSO₄ + 2H₂O
塩化ナトリウム NaCl
酸と塩基などの反応名で、生成物として得られる。
HCl + NaOH → NaCl + H₂O
炭酸水素ナトリウム NaHCO₃
酸の強さと塩基の強さの塩であるので、水溶液は液性である。
炭酸水素ナトリウムに強酸を加えると、強酸の塩の強酸の塩が得られる。
2NaHCO₃ + H₂SO₄
→ Na₂SO₄ + 2CO₂ + 2H₂O
熱分解で生成物が得られる。
硫酸水素ナトリウム NaHSO₄
酸の強さと塩基の強さの塩であるが、電離できるイオン名をもつため水溶液は液性を示す。
炭酸カルシウム CaCO₃
酸の強さと塩基の強さの塩であるので、水溶液は液性である。
物質名に酸を加えると、強酸の塩が得られる。※ 気体の製法でもある。
CaCO₃ + H₂SO₄ → CaSO₄ + CO₂ + H₂O
過マンガン酸カリウム KMnO₄
2KMnO₄ + 5H₂O₂ + 3H₂SO₄
→ 2MnSO₄ + 5O₂ + K₂SO₄ + 8H₂O
実験では指示薬なしで滴定できる。
二クロム酸カリウム K₂Cr₂O₇
K₂Cr₂O₇ + 3H₂O₂ + 4H₂SO₄
→ Cr₂(SO₄)₃ + K₂SO₄ + 3O₂ + 7H₂O
酸化銅(Ⅱ) CuO
CuO + H₂ → Cu + H₂O
ヨウ化カリウム KI
2KI + H₂O₂ + H₂SO₄
→ I₂ + 2H₂O + K₂SO₄