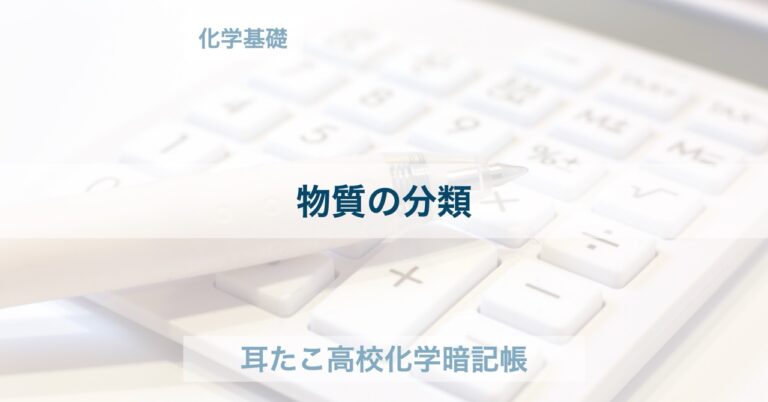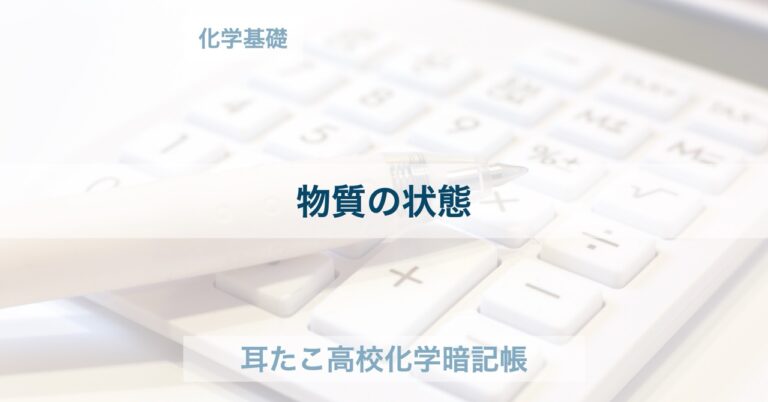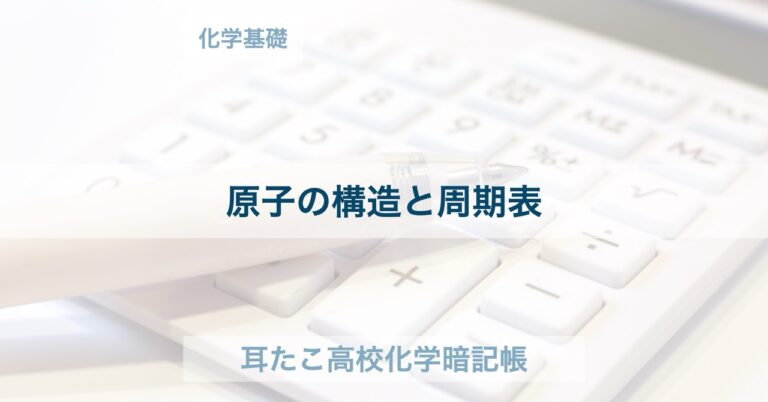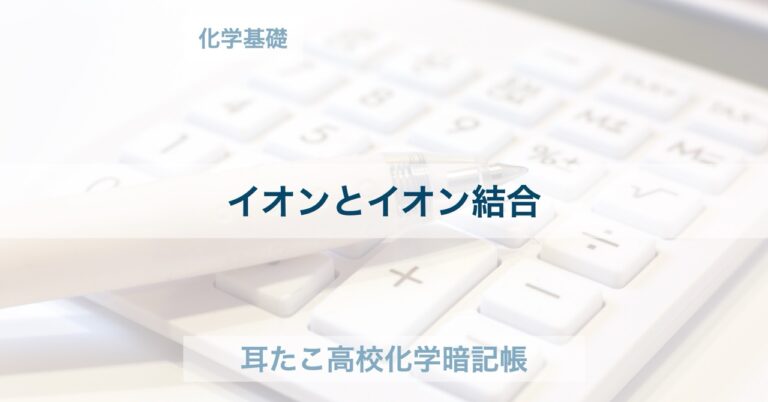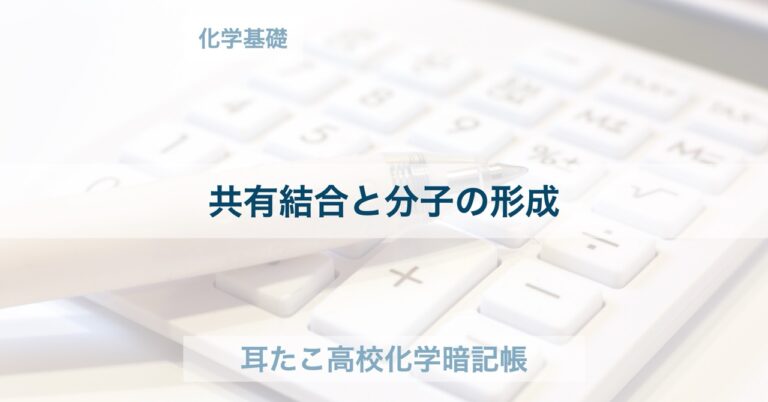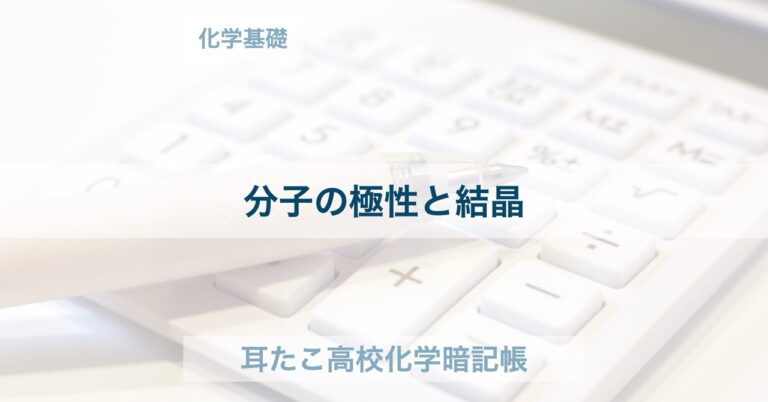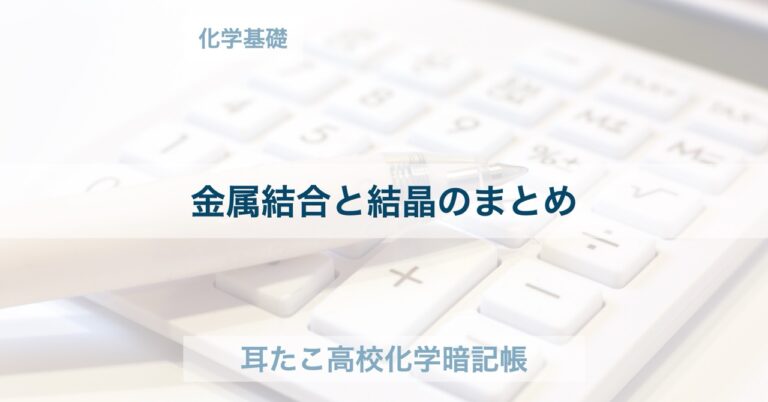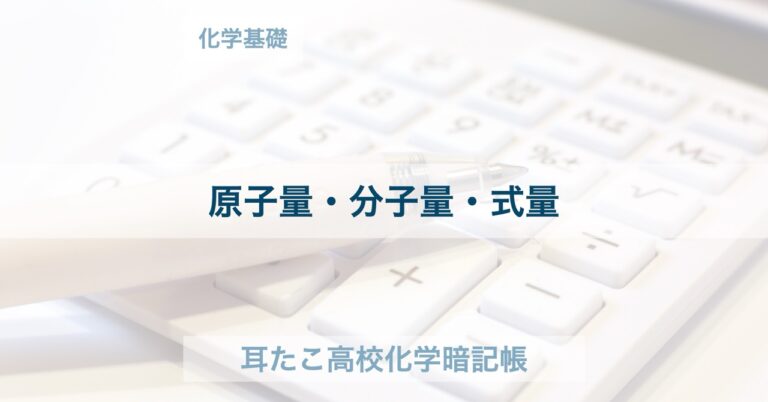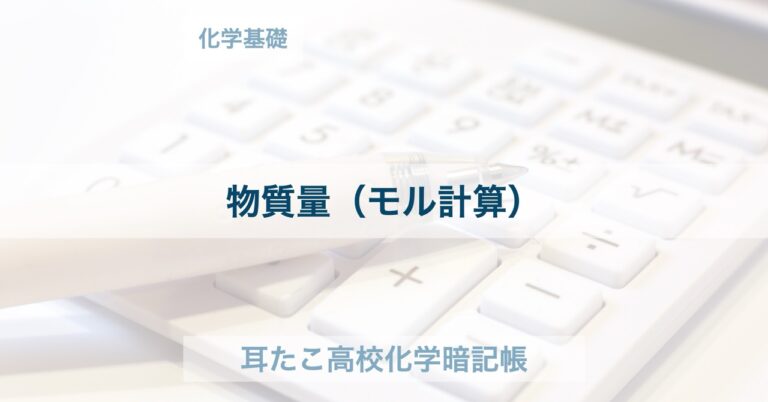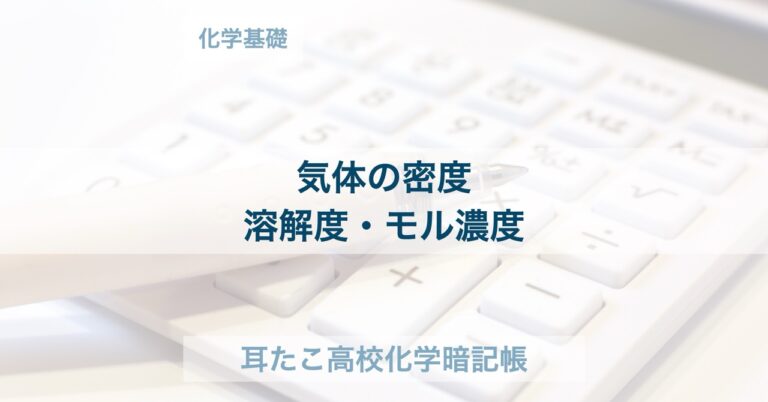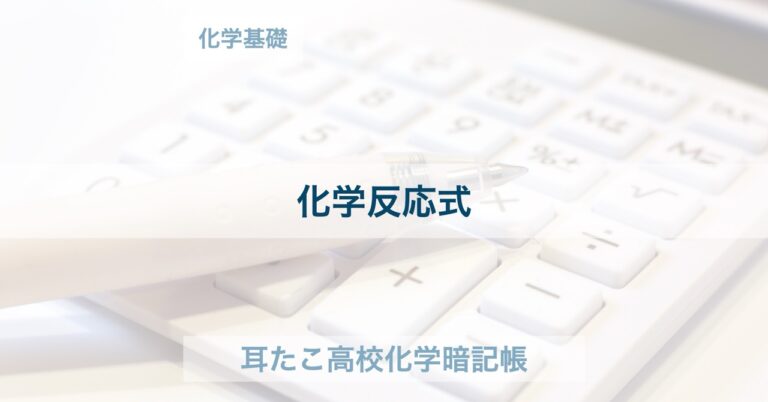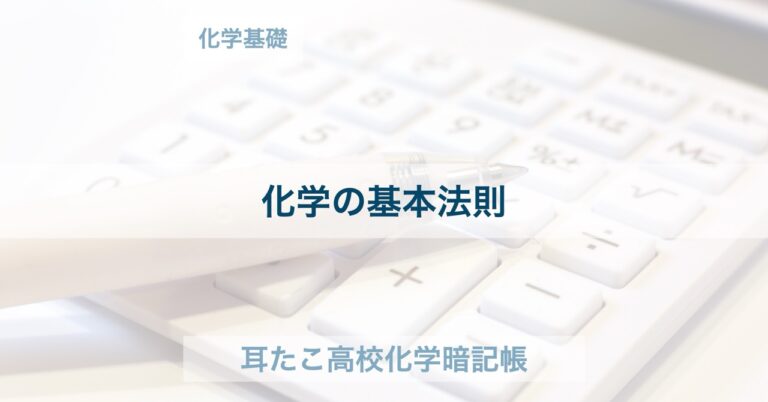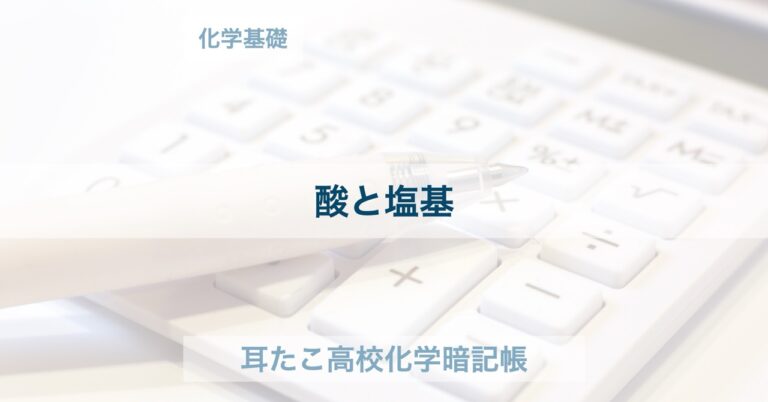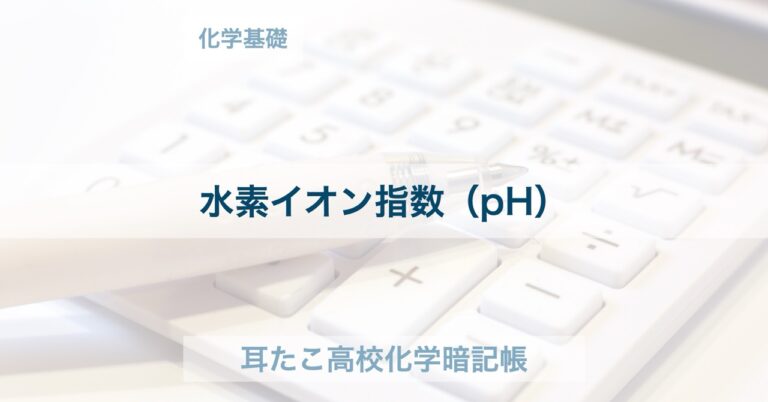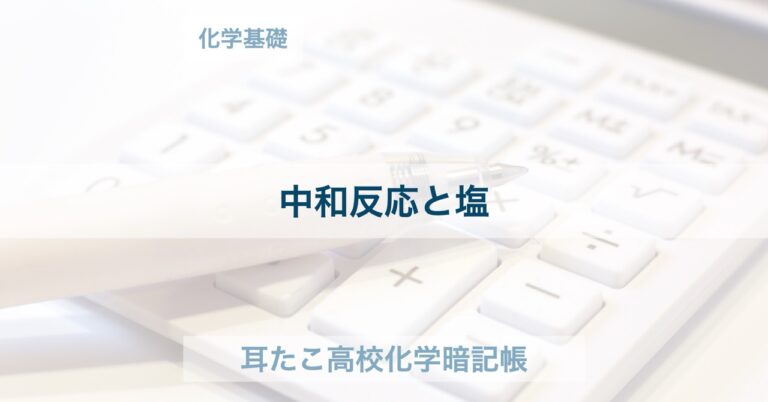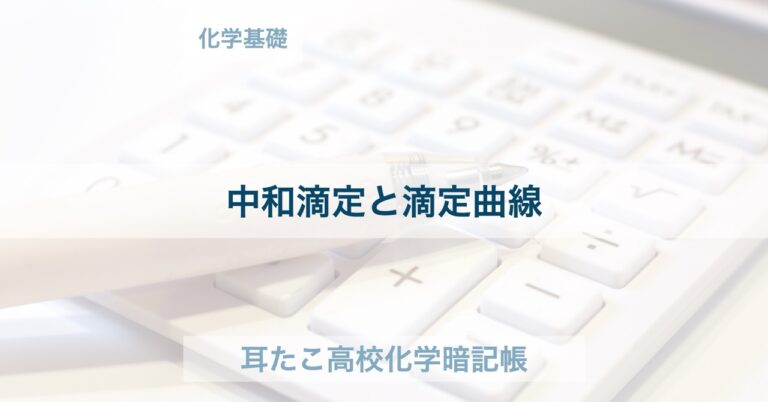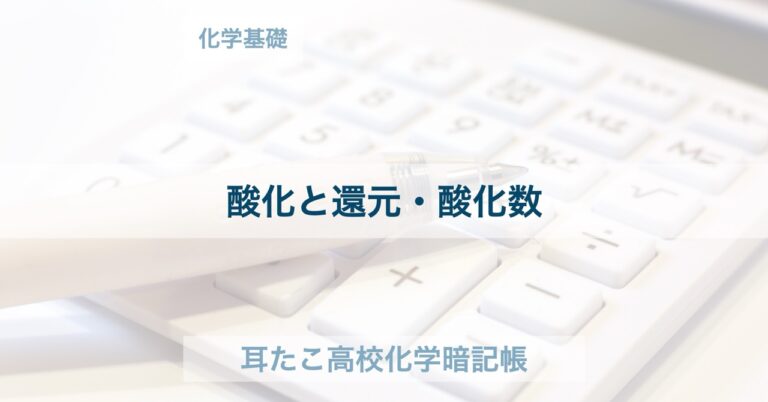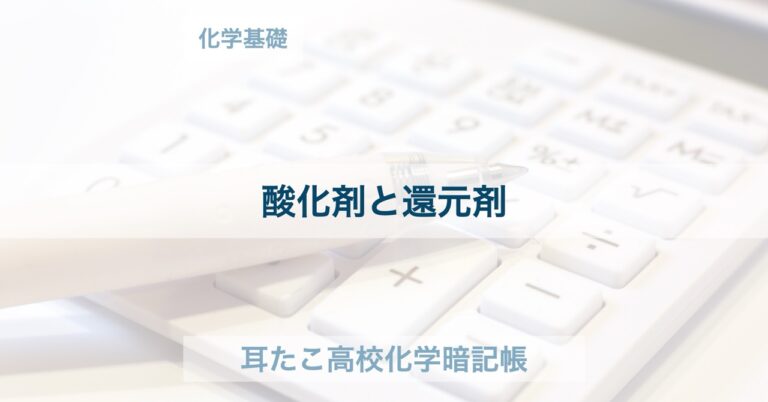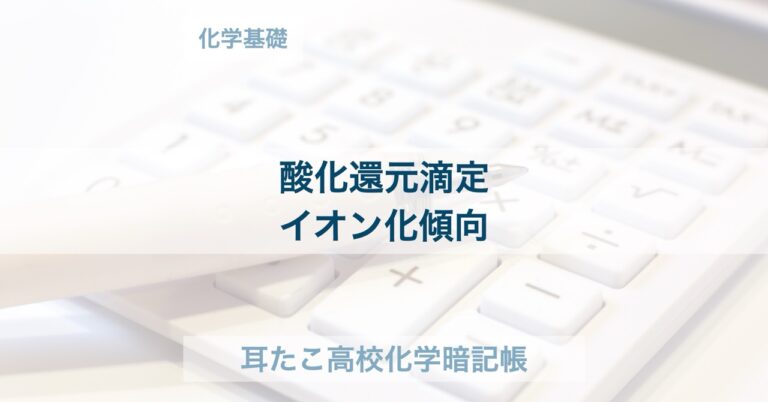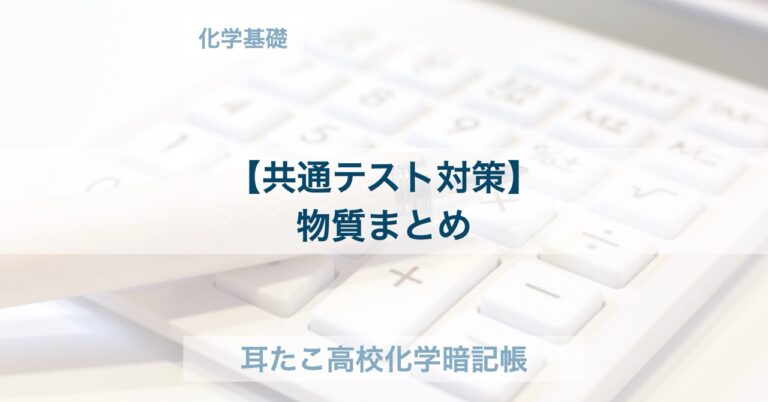スポンサーリンク
化学基礎分野単元一覧

- 耳たこ高校化学暗記帳の「化学基礎のまとめ」ページです。
- 四角い枠をクリックすると解答が表示され、下のボタンで一括表示・非表示の切替ができます。
- 耳たこ音読では音声ファイルを再生して要点を音読します。通学時間などのスキマ学習に最適です。
- 目次をクリックすると各セクションへ移動します。
目次
耳たこ音読まとめ|物質の構成と化学結合
■ 音声プレイヤー※音が出ます!
物質の構成と化学結合の分野の音声ファイルをまとめたものです。「物質の分類」から「結晶の種類と性質」までの音声が流れます。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
物質の構成と化学結合の分野の音声ファイルをまとめたものです。「物質の分類」から「結晶の種類と性質」までの音声が流れます。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
物質の分類
物質の分類
分類名は数の物質からなり、数以上の純物質が混ざったものを分類名という。純物質は同一条件での性質・性質・性質が一定であり、混合物は混合割合によってそれらが変化する。混合物、混合物、混合物、混合物などは混合物である。
分類名は数の元素からなる純物質で単体、単体、単体などは単体であり、分類名は数以上の元素からなる純物質で化合物、化合物などは化合物である。
混合物の分離
用語は、分類名から分類名を取り出す操作をいい、分離で得た物質から用語を取り除き、純度を高める操作を用語という。
操作は、液体とその液体に溶ける?固体を分ける操作であり、溶液を器具で静かにろ紙に伝わせ、器具の先はビーカーの内側に付ける。
操作は、液体を気体にして冷却し、再び状態として回収する操作であり、温度計の球部を枝付きフラスコの位置に合わせ、物質を入れて現象を防ぐ。また、リービッヒ冷却器に流す水は流し方へ流し、アダプターと三角フラスコの間は用語しない。
操作は、物性の異なる液体の混合物から、成分を順に分離する操作である。
操作は、用語が混じった固体を溶媒に溶かして、冷却することで純粋な用語を取り出す操作である。
操作は、目的物だけを溶かす用語を用いて、目的物を分離する操作である。
操作は、混合物中の性質の成分を一度気体にして冷却し固体とすることで、分離する操作であり、物質や物質は昇華性がある。
操作は物質への性質の違いを利用した分離の操作であり、操作はろ紙への吸着性を用いる。
元素と同素体
用語は物質をつくる基本成分で、世界共通の用語で表す。
同じ元素からなる単体で、性質がどう?ものを用語という。
元素の同素体には同素体、同素体、同素体がある。
元素の同素体には硬度電気を通す?同素体、硬度電気を通す?同素体、球状分子の同素体、筒状の同素体がある。
元素の同素体には同素体と同素体がある。
元素の同素体には性質で性質するので場所に保存する同素体と安定している同素体がある。
炎色反応
特定の元素を含む水溶液を炎の中に入れると炎の色が変わる。これを○○反応といい、元素は色、元素は色、元素は色、元素は色、元素は色、元素は色、元素は色となる。
物質の状態
物質の状態
物質を構成する粒子の運動を用語といい、温度が高いほど程度なる。熱運動によって粒子が空間に広がる現象を用語という。また、分子がお互いに引き合う力を用語という。
状態、状態、状態を物質の用語という。
固体は、粒子が構造配列し、熱運動は程度で分子間力が大小。液体は、熱運動が程度で粒子は○○的に動き、分子間力がはたらく。気体は、熱運動が程度空間を自由に運動し、分子間力は程度。
物質の用語には、固体が液体になる状態変化、液体が固体になる状態変化、液体が気体になる状態変化、気体が液体になる状態変化、固体が気体になる状態変化、気体が固体になる状態変化がある。
原子の構造と周期表
原子の構造と同位体
物質を構成する最小の粒子を粒子という。原子は電気的に○性で、用語で表される。原子は電荷が値の粒子と電荷が値の粒子からなる用語と、その周りに存在する電荷が値の粒子からなる。
粒子の数は元素によって決まった数で用語と等しい。粒子の数は原子によって異なる。粒子の数は陽子の数と等しい。
陽子と中性子と電子の用語は値で、粒子の質量は非常に小さい。
元素記号で表すとき、左上の数を用語といい、粒子の数と粒子の数の和となる。左下の数を用語といい、粒子の数や粒子の数と等しい。原子の種類は粒子の数で決まる。
同じ用語(粒子の数)をもち、用語(粒子の数)が異なる原子を用語という。同位体どうしの○○的性質はほぼ同じである。
同位体のうち、原子核が不安定で用語を放出して他の元素へと変わるものを用語という。
電子殻と電子配置
粒子は用語に存在し、内側から最大収容電子数が個数の殻、個数の殻、個数の殻、個数の殻がある。内側からn番目の最大収容電子数は式個である。電子が内側の殻から順に入ることを用語といい、それぞれの電子殻に最大数まで電子が入った状態を用語という。
最も外側の殻にある電子を用語といい、このうち化学反応に関与するものを用語という。分類名は価電子が値の安定な電子配置をもち、他の原子と結合しにくい。
代表的な原子の電子配置は、
ヘリウムHeは電子配置、
リチウムLiは電子配置、
フッ素Fは電子配置、
ネオンNeは電子配置、
ナトリウムNaは電子配置、
塩素Clは電子配置、
アルゴンArは電子配置、
カリウムKは電子配置となる。
周期表
元素を用語順に並べたものを用語といい、縦の列を用語、横の行を用語という。原型は人物が提案した。
1、2、13〜18族の元素を分類名といい、同じ用語で似た性質の元素が並ぶ。3〜12族の元素を分類名という。また、周期表の左下にいくほど性質が強く、右上にいくほど性質が強い。ただし、元素名は1族であるが分類である。
水素Hを除く1族元素を分類名といい、価数+イオンになりやすい。単体はやわらかく、融点が高低、密度が大小。
2族元素を分類名といい、価数+イオンになりやすい。
17族元素を分類名といい、価数+イオンになりやすい。単体は用語で、〇〇力が強い。
18族元素を分類名といい、価電子が値でイオンや化合物になりにくい。単体は用語である。
イオンとイオン結合
イオン
原子が粒子を失ったり、得たりすると用語を帯びて粒子となる。原子1個からなるイオンをイオンの種類、2個以上の原子が結合した粒子からなるイオンをイオンの種類という。
粒子の少ない原子は、電子を用語して用語となる。粒子の多い原子は、電子を用語用語となる。放出または受け取った電子の数をイオンの用語という。18族の分類名は価電子が個数でイオンになりにくい。
単原子イオンの用語は、用語がもっとも近い分類名と同じ電子配置となる。
単原子イオンには、H⁺、ヘリウムHeと同じ電子配置のLi⁺、ネオンNeと同じ電子配置のO²⁻、F⁻、Na⁺、Mg²⁺、Al³⁺、その他にS²⁻、Cl⁻、K⁺、Ca²⁺、Br⁻、I⁻、Ag⁺、Cu²⁺、Fe²⁺、Fe³⁺などがある。
多原子イオンには、NH₄⁺、H₃O⁺、OH⁻、NO₃⁻、HCO₃⁻、SO₄²⁻、CO₃²⁻、PO₄³⁻などがある。
イオン化エネルギーと電子親和力
電子個数を失って価数+イオンとなるのに必要なエネルギーを用語という。周期表では、位置に行くほどイオン化エネルギーが大きくなり、イオンの種類になりにくくなる。元素名が最大である。
電子個数を受け取って価数+イオンになるときに放出するエネルギーを用語という。周期表では、分類名を除いて位置に行くほど電子親和力が大きくなり、イオンの種類になりやすくなる。
原子とイオンの大きさ
用語元素では、周期表の位置にいくほど原子の大きさは大小なる。用語の元素では、周期表の位置にいくほど原子の大きさは大小なる。
原子は、用語になると原子の大きさは大小なり、用語になると原子の大きさは大小なる。
同じ用語をとる用語では、用語が多いほど(用語が大きいほど)、イオンの大きさは大小なる。
イオン結合とイオン結晶
用語と用語の間に働く○○力(○○力)による結合を結合名という。
イオン結合によってできる結晶を結晶名といい、融点は高低、硬度は高低が性質。結晶では電気を通す?が、液体や状態では通す?。水に溶けやすい?ものが多い。
イオンからなる物質や金属、結晶名などを最も簡単な用語で表した式を用語という。
組成式は、化合物全体で電気的に性質になるように、用語を決める。
NaCl、Mg(OH)、AgNO₃、NaHCO₃、Al₂O₃、Ca₃(PO₄)₂などがある。
共有結合と分子の形成
共有結合とその構造
粒子同士が互いの粒子を共有することでできる結合を用語といい、それぞれの原子は安定した分類名と同じ用語となり、分子を作る。
水素分子H₂では水素原子が粒子を1つずつ共有し、原子原子と同じ電子配置となり用語する。
水分子H₂Oでは酸素原子が2つの水素原子と粒子を共有して原子原子と同じ電子配置となり、水素原子は原子原子と同じ電子配置となり用語する。
分子式・電子式・構造式
分子を表す化学式を○○式といい、用語と個数を右下に添えて書く。
元素記号の周囲に用語を点で示した式を○○式といい、電子が対になったものを用語、対になっていないものを用語という。
結合で共有している電子対を用語、共有していない電子対を用語といい、結合している共有電子対を用語で表した式を○○式という。また、共有電子対が1組の結合を用語、2組を用語、3組を用語という。
原子から出る用語の本数を用語といい、基本的に用語の数に等しい。
配位結合
用語で、一方の原子のみが用語を出してそれを共有する結合を用語という。化合物がイオンを受け取り生成したイオン、化合物がイオンを受け取り生成したイオンがあり、生成したイオンは性質している。
分子の極性と結晶
分子の極性
用語は、けつごうしている原子間で用語を引きつける強さを数値にしたものであり、分類名を除いた周期表の位置ほど大きく、元素名が最大となる。
水素H₂のように同種の原子間では用語の差がないため用語は生じないが、塩化水素HClのように異種の原子間では、用語の大きい原子に用語が偏り、用語をもつ。
多原子分子では、用語が結合の極性を打ち消し合う構造であれば分類名、打ち消されない構造であれば分類名となる。
水素H₂は形状で極性or無極性であり、窒素N₂も形状で極性or無極性である。塩化水素HClは形状であるが極性or無極性となる。
二酸化炭素CO₂は形状で極性or無極性であるが、水H₂Oは形状で極性or無極性となる。
アンモニアNH₃は形状で極性or無極性で、メタンCH₄は形状で極性or無極性である。
分子結晶と共有結合の結晶
結晶は、構成が○○力で規則正しく配列した結晶で、やわらかくもろく、融点が高低、電気を通す?。物質、物質、物質などがある。
結晶は、多数の構成が結合した結晶で、硬度が高低、融点が高低。電気を通す?が、物質は電気を通す。物質、物質などがある。
金属結合と結晶のまとめ
金属結合と金属結晶
金属は、金属原子が多数集まり、用語が自由に動き回る構造をもつ。これらの電子を用語といい、すべての金属原子に共有されて、用語で原子同士が結びつく。金属は性質をもち、○性・○性が大きく、○○性と○○性がよい。
結晶の種類と性質
結晶は、分類の原子が結合でつながった結晶で、融点は高低、電気を通さないが、物質は電気を通す。水には溶ける?。物質、物質などがある。
結晶は、粒子と粒子が結合で配列した結晶で、融点は高低。固体は電気を通す?が、液体や水溶液は電気を通す?。水に溶ける?ものが多い。塩化ナトリウムNaCl、炭酸カルシウムCaCO₃などがある。
結晶は、粒子と粒子からなる結晶で、結合は結合である。融点は高低ものが多く、電気を通す?、水には溶ける?。鉄Fe、銅Cu、アルミニウムAlなどがある。
結晶は、原子が結合した粒子同士が○○力で配列した結晶で、融点は高低、電気を通す?、水に溶ける?。物質、物質などがある。
耳たこ音読まとめ|物質量と化学反応式
■ 音声プレイヤー※音が出ます!
物質量と化学反応式の分野の音声ファイルをまとめたものです。「原子量・分子量・式量」から「化学の基本法則」までの音声が流れます。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
物質量と化学反応式の分野の音声ファイルをまとめたものです。「原子量・分子量・式量」から「化学の基本法則」までの音声が流れます。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
原子量・分子量・式量
相対質量と原子量
元素1個の質量を数としたときの、各原子の質量比を原子の用語といい、単位は付けない。
相対質量の求め方は、用語の比と原子1個の用語の比が等しいことを用いて計算する。
2種類以上の用語がある元素の用語は、同位体の用語 × 用語の和で求める。
分子量と式量
分子を構成するすべての原子の用語の和を用語という。
水H₂Oでは、水素原子個数と酸素原子個数より、分子量は18となる。
○○式で表されるイオン結晶や金属などの用語を用語といい、組成式を構成するすべての原子の用語の和で表す。用語は無視してよい。
塩化ナトリウムNaClでは、塩化物イオン個数とナトリウムイオン個数より、式量は58.5となる。
物質量(モル計算)
物質量
原子、分子、イオンなどの粒子の個数の集まりを単位量とし、この量を用語という。また、6.0×10²³を用語という。H₂分子0.5molだと、分子の個数は個数となる。
物質1molあたりの質量は、用語に単位gを付けた値となる。このときの質量を用語g/molという。H₂分子0.5molだと、分子量が2.0より数値となる。
気体1molあたりの体積は、気体の種類によらずに、用語で体積の値となる。この体積を用語L/molという。H₂分子0.5molだと、標準状態で数値となる。
気体の密度・溶解度・モル濃度
気体の密度
固体や液体の密度g/cm³は、量・単位あたりの量・単位で表す。また、気体の密度g/Lは、標準状態で量・単位あたりの量・単位で表す。よって、標準状態の気体1molの体積は数値で一定であるので、気体の密度の大小は用語の大小と等しくなる。
溶解度
物質を溶かす液体を用語、溶けた物質を用語、できた均一の液体を用語という。また、溶媒100gあたりに溶ける溶質の最大質量を用語といい、このときの溶液を用語という。
質量パーセント濃度とモル濃度
溶液の量・単位に対する溶質の量・単位の割合を百分率で表した値を用語という。また、量・単位あたりに溶けている溶質の量・単位を用語という。
化学反応式
化学反応式
物質の反応を化学式を用いて表した式を○○式といい、反応する物質を用語、反応してできる物質を用語という。
化学反応式は左辺に用語、右辺に用語を書き、「→」で結び、両辺の何の数が同じになるように係数を付ける。このとき、化学反応式の用語は、反応物や生成物の用語と等しくなる。さらに、気体の場合は用語も等しくなる。
○○式とは、反応に関係する粒子だけを表した式であり、両辺の用語の総和が等しくなるようにする。
化学の基本法則
化学の基本法則
化学の基本法則には、基本法則(人物、反応の前後において、反応に関係した物質の用語の総和は変わらない。)、
基本法則(人物、化合物を構成する用語の比は常に一定である。)、
基本法則(人物、2種の元素A,Bからなる化合物が2種類以上あるとき、元素Aの一定量と化合する元素Bの用語の間には簡単な用語が成立する。)があり、
これらに基づいて、基本法則(すべての物質は、分割できない粒子という粒子でできている。)が提唱された。
ただし、原子説は基本法則(人物、すべての気体は、同温・同圧のもとで用語であれば、気体の種類に関係なく同数の分子を含む。)に矛盾するので、
基本法則(すべての気体は、同種あるいは異種の原子が結合した粒子という粒子からなる。)と
基本法則(すべての気体は、同温・同圧のもとで同体積であれば、気体の種類に関係なく同数の粒子を含む。)が提唱された。
耳たこ音読まとめ|酸・塩基と酸化還元反応
■ 音声プレイヤー※音が出ます!
酸・塩基と酸化還元反応の分野の音声ファイルをまとめたものです。「酸と塩基」から「酸化還元滴定・イオン化傾向」までの音声が流れます。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
酸・塩基と酸化還元反応の分野の音声ファイルをまとめたものです。「酸と塩基」から「酸化還元滴定・イオン化傾向」までの音声が流れます。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
酸と塩基
酸と塩基
酸と塩基の人物の定義は、水溶液中でイオンを出す物質を酸、イオンを出す物質を塩基とする。人物の定義では、酸はイオンを用語物質、塩基は水素イオンH⁺を用語物質である。
水溶液中で酸がイオンを、塩基がイオンを放出している状態を用語といい、放出する水素イオンH⁺の数を用語、放出する水酸化物イオンOH⁻の数を用語という。
溶けた酸(塩基)の用語に対する用語している酸(塩基)の用語の割合を用語といい、電離度が数値に近いほど用語となり、電離度が大小ほど用語となる。
酸と塩基の種類
1価の強酸には1価の強酸、1価の強酸、1価の弱酸には1価の弱酸があり、2価の強酸には2価の強酸、2価の弱酸には2価の弱酸、3価の中酸には3価の中酸 がある。
1価の強塩基には1価の強塩基、1価の強塩基があり、1価の弱塩基には1価の弱塩基がある。2価の強塩基には2価の強塩基 があり、2価の弱塩基には2価の弱塩基、2価の弱塩基がある。
水素イオン指数(pH)
水素イオン濃度と水酸化物イオン濃度
酸性の水溶液中の水素イオンのモル濃度を用語記号といい、水溶液の用語×濃度×用語で求める。また、塩基性の水溶液中の水酸化物イオンのモル濃度を用語記号といい、水溶液の用語×濃度×用語で求める。ただし、用語や用語の電離度は1として計算する。
水素イオン指数pH
水素イオン濃度の大小を示し、酸性・塩基性の強弱を表す数値を水素イオン指数用語という。水素イオン濃度[H⁺]が1.0×10⁻ⁿmol/Lのとき、値となる。
pH<7のとき、液性は液性で、0に近いほど酸性が強い。pH=7のとき、液性は液性である。pH>7のとき、液性は液性で、14に近いほど塩基性が強い。
酸性の水溶液を10ᵃ倍に薄めると、pHが値だけ大きくなるが、中性の値より大きくならない。
中和反応と塩
中和反応
酸のイオンと塩基のイオンから物質が生成し、同時に物質が生成する反応を反応という。
塩には酸由来のHも、塩基由来のOHも残っていない分類名、炭酸水素ナトリウムNaHCO₃などの酸由来のHが残る分類名、塩基由来のOHが残る分類名がある。
塩の水溶液の液性は、強酸と強塩基の塩は液性だが、分類の硫酸水素ナトリウムNaHSO₄は液性を示す。弱酸と強塩基の塩は液性を示し、強酸と弱塩基の塩は液性を示す。
中和反応の量的関係
中和反応では、酸・塩基の強弱に関係なく、酸から生じるイオンの物質量と塩基から生じるイオンの物質量が等しくなる。これより、酸の用語×用語×用語と塩基の用語×用語×用語が等しい式を立てる。
また、片方が物質の固体で質量が与えられた場合は、その物質の用語を求めて、用語×用語×用語と用語×用語が等しい式を立てる。
中和滴定と滴定曲線
中和滴定
濃度がわかる溶液を用いて、未知の酸または塩基が過不足なく用語する体積から濃度を決定する操作を操作という。
中和滴定の実験器具の実験器具は一定量の溶液の用語を正確に量り取り、用語をして使う。実験器具は、正確な用語の水溶液を作るのに用いて、純水ですすぎ、用語使う。実験器具は、濃度が未知の溶液を入れるのに用いて、純水ですすぎ、用語使う。実験器具は、濃度がわかる溶液を用語して、溶液の正確な用語を量るのに用いて、用語をして使う。
水溶液の用語で色が変わる物質を用語といい、色が変わる範囲を用語という。指示薬は、酸性側で反応し色から色となる。指示薬は、塩基性側で反応し色から色となる。
中和滴定の手順は、濃度が未知の溶液を実験器具で正確な体積だけ量り取り、実験器具に入れ、用語を加える。次に、実験器具に正確な濃度の溶液を作り、実験器具に入れる。実験器具から濃度がわかる溶液を実験器具に滴下して、体積を正確に読み取る。
滴定曲線
中和滴定で滴下する溶液の量とpHの関係を表す曲線を用語といい、中和が終了する点を用語という。この中和点前後でpHが急激に変化するので、この範囲を用語で測り中和点を求める。
強酸に強塩基を滴定するときは、中和点は約pHの値で、pHが変化する範囲が広いので、指示薬は指示薬または指示薬を用いる。
弱酸に強塩基を滴定するときは、中和点はpH=7より大小、範囲が液性側に寄るので、指示薬は指示薬を用いる。
強酸に弱塩基を滴定するときは、中和点はpH=7より大小、範囲が液性側に寄るので、指示薬は指示薬を用いる。
酸化と還元・酸化数
酸化と還元・酸化数
用語の定義は、酸素Oを用語、水素Hや電子e⁻を用語、酸化数が用語することである。用語の定義は、酸素Oを用語、水素Hや電子e⁻を用語、酸化数が用語することである。
酸化反応と還元反応は逆の化学反応で、常に用語に起こっており、この反応を○○反応という。
物質中の原子がどのくらい酸化されているかを示す数値を用語という。
酸化数は、単体や化合物全体は数となり、単原子イオンや多原子イオンは用語の数値と等しくなる。
化合物中の水素Hは数、酸素Oは数であるが、例外としてNaHのHは数、H₂O₂のOは数となる。
また、アルカリ金属のNa、Kなどは数、アルカリ土類金属のCa、Baなどは数である。
酸化剤と還元剤
酸化剤と還元剤
物質は相手を用語して、自分は用語され、電子を用語、酸化数が増減する物質であり、物質は、相手を用語して、自分は用語され、電子を用語、酸化数が増減する物質である。
酸化剤の酸化剤KMnO₄は反応前後で色から色になり、酸化剤K₂Cr₂O₇は反応前後で色から色となる。
還元剤には還元剤H₂Sや還元剤H₂C₂O₄がある。
また、酸化剤の物質H₂O₂は、過マンガン酸カリウムKMnO₄や二クロム酸カリウムK₂Cr₂O₇に対しては用語として働く。
還元剤の物質SO₂は、硫化水素H₂Sに対しては用語として働く。
酸化還元反応の化学反応式
酸化還元反応の化学反応式において、反応式中の酸化数が増減し、相手を還元している物質は物質であり、酸化数が増減し、相手を酸化している物質は物質である。
酸化還元滴定・イオン化傾向
酸化還元滴定
濃度がわかる○○剤(または○○剤)を用いて、濃度が未知の○○剤(または○○剤)の水溶液の濃度を求める操作を用語という。このとき、酸化剤に酸化剤を用いると、色から色になるので、指示薬を使わないで滴定できる。
酸化還元滴定での量的関係を求めるときは、酸化剤が用語電子e⁻の物質量と還元剤が用語電子e⁻の物質量が等しいことを用いる。
金属のイオン化傾向
単体の金属がイオンになろうとする性質を金属の用語といい、大きい順に並べてものを金属の用語という。
金属 > 金属 > 金属 > 金属 > 金属 > 金属 > 金属 > 金属 > 金属 > 金属 > 金属 > 気体 > 金属 > 金属 > 金属 > 金属 > 金属 の順番となる。
空気との反応は、リチウムLi〜ナトリウムNaは用語で反応し、マグネシウムMgとアルミニウムAlは用語により反応し、亜鉛Zn〜水銀Hgは用語により反応する。
水との反応は、リチウムLi〜ナトリウムNaは用語で反応し気体を発生し、マグネシウムMgは熱水と反応し、アルミニウムAl〜鉄Feは高温の用語で反応する。
酸との反応は、リチウムLi〜鉛Pbは酸や酸と反応して気体を発生し、銅Cu〜銀Agは酸や酸と反応し、白金Ptと金Auは物質に溶ける。
ただし、鉛Pbは、酸や酸と反応すると水に溶けない膜をつくり反応しなくなり、アルミニウムAl、鉄Fe、ニッケルNiは濃硝酸で用語となり反応しない。
電池の構造と種類
イオン化傾向の大小金属板を◯極、大小金属板を◯極として、電解質の水溶液に入れたとき、エネルギーを得る装置を用語という。負極では、導線に向かって電子が流れ出し○○反応が起こり、正極では、導線から電子が流れこんで○○反応が起こる。ただし、電流は正極から負極に流れる。
正極と負極との電位差を用語という。
放電すると再利用できない電池を◯◯電池といい、電池などがある。また、充電すると繰り返し使える電池を◯◯電池または◯電池といい、電池などがある。
耳たこ音読まとめ|【共通テスト対策】物質まとめ
■ 音声プレイヤー※音が出ます!
【共通テスト対策】物質まとめの音声ファイルをまとめたものです。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
【共通テスト対策】物質まとめの音声ファイルをまとめたものです。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!
ナレーション 音読さん
非金属元素の単体と化合物①
水素H₂は、分子の形で極性or無極性である。製法は、金属に酸を加えると発生する。燃やすと生成物が生成する。水素イオンH⁺は価数のイオンの種類である。
酸素O₂は、同素体に同素体がある。製法は、化合物に化合物を加えると発生する。物を現象させる働きがある。酸化物イオンO²⁻は価数のイオンの種類である。
窒素N₂は、分子の形で極性or無極性である。空気中に約体積比含む。
炭素Cには、同素体として結晶の種類で硬く電気を通さない同素体、やわらかく電気を通しやすい同素体、球状分子の同素体、筒状の同素体がある。
硫黄Sには、同素体として同素体、同素体、同素体がある。
リンPには、同素体として猛毒で性質するので水中に保存する同素体と、安定している同素体がある。
フッ素F₂は、分類名で1価の陰イオンのイオン名になりやすく、単体は分子の種類である。用語は最大である。
塩素Cl₂は、分類名で1価の陰イオンのイオン名になりやすく、単体は分子の種類であり、○○剤として働く。
臭素Br₂は、分類名で1価の陰イオンのイオン名になりやすく、単体は分子の種類であり、○○剤として働く。
ヨウ素I₂は、分類名で1価の陰イオンのイオン名になりやすく、単体は分子の種類で、結晶の種類となり、○○性がある。○○剤として働く。
ヘリウムHeは、分類名で価電子が数値でイオンや化合物になりにくく、単体は分子の種類である。最外殻電子数は数値で、用語が最大である。
ネオンNeは、分類名で価電子が数値でイオンや化合物になりにくく、単体は分子の種類である。最外殻電子数は数値である。
アルゴンArは、分類名で価電子が数値でイオンや化合物になりにくく、単体は分子の種類である。最外殻電子数は数値である。
非金属元素の単体と化合物②
水H₂Oは、分類の化合物で分子の形の極性or無極性である。電気分解では陽極に気体、陰極に気体が発生する。水は水素イオンH⁺と結合して安定したイオン名となる。反応名では酸のH⁺と塩基のOH⁻から水H₂Oが生成する。
塩化水素HClは、分子の形だが用語の差により極性or無極性である。水溶液は酸で価数と強さである。金属との反応は、イオン化傾向の金属〜金属と反応して気体を発生する。電気分解では陽極に気体、陰極に気体が発生する。
硝酸HNO₃は、価数と強さである。金属との反応は、イオン化傾向の金属〜金属と反応し、金属や金属とは反応しない。
硫酸H₂SO₄は、価数と強さである。物質は金属〜金属と反応して気体を発生する。物質は金属〜金属と反応し、金属や金属とは反応しない。
シュウ酸H₂C₂O₄は、価数と強さである。○○剤として働く。
リン酸H₃PO₄は、価数と強さである。イオン名は3価の陰イオンである。
酢酸CH₃COOHは、価数と強さである。
二酸化炭素CO₂は、物質(別名)に酸を加えると発生し、試薬を白く濁らせる。分子の形で、極性or無極性である。固体の固体名は結晶の種類で、やわらかくもろく、融点は低く、電気を通しにくい。
アンモニアNH₃は、物質に物質を加えると発生する。臭いがあり、水に溶けやすさて、価数と強さとなる。アンモニアは水素イオンH⁺と結合し、安定したイオン名となる。
メタンCH₄は、分子の形の極性or無極性である。
過酸化水素H₂O₂は、○○剤として働くが、酸化剤や酸化剤に対しては○○剤として働く。物質に過酸化水素水を加えると気体が発生する。
二酸化硫黄SO₂は、還元剤であるが、化合物に対しては○○剤として働く。
硫化水素H₂Sは、○○剤である。
ケイ素Siは、結晶の種類で、融点は非常に高く、電気を通さず、水に溶けない。性質の性質を示し、分類ではない。
二酸化ケイ素SiO₂は、結晶の種類で、融点は非常に高く、電気を通さず、水に溶けない。
金属元素とイオン化傾向①
リチウムLiは、1族元素の分類名に分類され、イオン名は1価の陽イオンである。炎色反応は色となる。空気とは条件で速やかに反応して酸化し、水とは条件で反応して気体を発生する。酸や酸と反応して水素を発生する。
カリウムKは、1族元素の分類名に分類され、イオン名は1価の陽イオンである。炎色反応は色となる。空気とは条件で速やかに反応して酸化し、水とは条件で反応して気体を発生する。
カルシウムCaは、2族元素の分類名に分類され、イオン名は2価の陽イオンである。炎色反応は色となる。空気とは条件で速やかに反応して酸化し、水とは条件で反応して気体を発生する。酸や酸と反応して水素を発生する。
ナトリウムNaは、1族元素の分類名に分類され、イオン名は1価の陽イオンである。炎色反応は色となる。空気とは条件で速やかに反応して酸化し、水とは条件で反応して気体を発生する。酸や酸と反応して水素を発生する。
マグネシウムMgは、2族元素の分類名に分類され、イオン名は2価の陽イオンである。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは条件と反応し、酸や酸と反応して水素を発生する。
アルミニウムAlは、イオン名が3価の陽イオンであり、合金に合金がある。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは高温の条件で反応し、酸や酸と反応して、気体を発生する。ただし、濃硝酸では性質となり溶けない。
亜鉛Znは、イオン名が2価の陽イオンであり、鉄Feに亜鉛Znをめっきしたものを用語という。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは高温の条件で反応し、酸や酸と反応して、気体を発生する。
鉄Feは、2価の鉄(Ⅱ)イオンFe²⁺と3価の鉄(Ⅲ)イオンFe³⁺がある。鉄FeにスズSnをめっきしたものを用語といい、亜鉛Znをめっきしたものを用語という。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは高温の条件で反応し、酸や酸と反応して、気体を発生する。ただし、濃硝酸では性質となり溶けない。
金属元素とイオン化傾向②
ニッケルNiは、空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは反応?。酸や酸と反応して、気体を発生するが、濃硝酸では性質となり溶けない。
スズSnは、鉄FeにスズSnをめっきしたものを用語という。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは反応?。酸や酸と反応して、気体を発生する。
鉛Pbは、イオン名が2価の陽イオンである。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは反応?。酸や酸を発生するが、水に溶けない膜をつくり反応?。
銅Cuは、イオン名が2価の陽イオンであり、炎色反応は色である。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置すると用語をつくる。水とは反応?。酸や酸とは反応する。
水銀Hgは、常温で状態である。空気とは条件により反応して酸化し、常温で放置しても反応?、水とも反応?が、酸や酸とは反応する。
銀Agは、イオン名が1価の陽イオンである。空気とは常温で放置しても反応?、水とも反応?。酸や酸とは反応する。
白金Ptは、空気とは常温で放置しても反応?、水とも反応?。王水には溶ける。
金Auは、空気とは常温で放置しても反応?、水とも反応?。王水には溶ける。
ストロンチウムSrは、2族元素で分類名に分類され、炎色反応は色となる。
バリウムBaは、2族元素で分類名に分類され、炎色反応は色となる。
イオン結合の化合物
水酸化ナトリウムNaOHは、価数と強さで酸と中和反応する。
水酸化カリウムKOHは、価数と強さで酸と中和反応する。
水酸化カルシウムCa(OH)₂は、価数と強さで酸と中和反応する。
水酸化マグネシウムMg(OH)₂は、価数と強さで酸と中和反応する。
水酸化銅(Ⅱ)Cu(OH)₂は、価数と強さで酸と中和反応する。
塩化ナトリウムNaClは、結合している結晶で、塩の分類である。塩酸HClと水酸化ナトリウムNaOHなどの反応名で、生成物として得られる。
炭酸水素ナトリウムNaHCO₃は、塩の分類であり、酸の強さと塩基の強さの塩であるので、水溶液は液性である。炭酸水素ナトリウムNaHCO₃に強酸を加えると、強酸の塩の強酸の塩が得られる。また、熱分解で生成物が得られる。
硫酸水素ナトリウムNaHSO₄は、塩の分類である。酸の強さと塩基の強さの塩であるが、電離できるH⁺をもつため水溶液は液性を示す。
炭酸カルシウムCaCO₃は、別名ともいわれ、酸の強さと塩基の強さの塩であるので、水溶液は液性である。炭酸カルシウムに酸を加えると、強酸の塩の強酸の塩が得られる。これは、気体の製法でもある。
過マンガン酸カリウムKMnO₄は、○○剤であり、反応前後で色から色となる。実験では指示薬なしで滴定できる。
二クロム酸カリウムK₂Cr₂O₇は、○○剤であり、反応前後で色から色となる。
酸化銅(Ⅱ)CuOは○○剤として働き、金属となる。
ヨウ化カリウムKIは○○剤として働き、単体となる。